VOL.38
高齢者医療に携わって20年。
急性期病院の中の療養病棟で
患者と家族の希望を叶える日々
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 療養病棟
瀧宮 顕彦氏(56歳)
広島県出身

- 1982年
- 東京医科大学卒業
同大学第二内科入局
同大学大学院入学 - 1983年
- 社会保険鰍沢病院循環器内科入職
- 1992年
- 医療法人社団三秀会青梅三慶病院循環器内科入職
- 1994年
- 医療法人社団東光会西東京中央総合病院(当時:田無第一病院)循環器内科入職
- 2011年
- 医療法人社団康明会康明会病院内科入職
- 2012年
- 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院療養病棟入職
どれだけ自分が求められているか。その度合いによって、やりがいは大きく変わる。東京西徳洲会病院療養病棟部長の瀧宮顕彦氏は、20年にわたり高齢者医療に尽力してきた。一度は、「ここに骨を埋めよう」と思う病院に在籍しながらも、現在の病院に転職したのは自分がいる必要性を感じたからだ。急性期中心の病院ゆえに療養病棟の専属医が不在である様子に、これまでの経験を生かしたいと考えた。転職して2年。病棟スタッフと協力しながら、患者・家族の希望を叶える日々は、やりがいに満ちている。
リクルートドクターズキャリア5月号掲載
BEFORE 転職前
新たに立ち上がる療養病棟を軌道に乗せるために
長年の経験が役に立った。
患者との信頼関係を築き病院職員の意欲を高める
高齢者医療をとりまく環境は、この数年で大きく変化した。最近では、一つのキャリアとして療養型病院に転職する医師も増えてきたが、東京西徳洲会病院療養病棟部長の瀧宮顕彦氏は、この道20年のベテランである。1982年に東京医科大学を卒業後、しばらくは同大学病院循環器内科や、関連病院に勤務し、卒後10年目に高齢者医療を中心とする青梅三慶病院(東京都青梅市)へ入職した。その後、医局派遣で半年ほど西東京中央総合病院(当時:田無第一病院)の急性期医療に携わるも、任務終了と同時に医局を離れ、循環器科医としてのキャリアに終止符を打つ。
「大学病院では、ほとんど研究ばかりでしたから、少なからず急性期の臨床への心残りがありました。しかし、そうした思いは田無第一病院での経験によって解消され、自分の性格や診療スタイルに合った高齢者医療に進む気持ちが固まりました」 同級生の紹介で大久野病院(東京都・日の出町)に入職したのは94年。当時は療養型病院という呼称は馴染みがなく、「老人病院」と呼ばれていた。入院患者のほとんどは在宅療養が困難になった高齢者で、家族は自宅で面倒を見られないことへの後ろめたさを抱えていることが多かった。また、病院職員も必ずしもモチベーションが高いとは言えなかった。
「患者を治療しようにも、家族が拒否するケースがありました。医師や看護師たちも医療に対してあまり積極的ではありませんでした」
瀧宮氏は、患者にとって望ましい医療を実現すべく、現場の改善に奔走した。家族が見舞いに来た時は、しっかり面会の時間を確保して、家庭内の事情や、患者のバックグラウンドをヒアリングした。あまり見舞いに来ない家族には、個別に連絡をして来てもらうこともあった。
「家庭内のやむを得ない理由で長期入院させているケースもあり、家族とのコミュニケーションは極めて困難でした。まずは丁寧な医療サービスを提供し、『この先生なら信頼できる』と思ってもらえるように、関係を構築していきました」
入職から3年目には副院長に就任し、「自分が引っ張っていかなければ」という思いが強かった瀧宮氏。日々、病院を改善するための努力を重ねた成果は、入職7~8年目から肌で感じることができた。
「意欲のある医師が増え、医療の質が向上しました。また、社会状況の変化によって療養型病院という呼称が一般化し、リハビリや在宅支援事業も手がけることになりました。退院は難しいと思っていた患者が、適切なケアによって退院できた様子を見るのはうれしかったですね」
大久野病院には17年間にわたって勤務し、療養型病院の標準的な運営方法を身につけた。新たなキャリアを進むべく医師転職会社を介して康明会病院(東京都日野市)に転職したのは2011年。同院は、在宅医療に力を入れる医療法人の傘下にある。瀧宮氏は「これまで培ってきた経験を生かしながら、骨を埋めるつもりでした」と振り返る。
「ここに骨を埋めよう」と思ったあとの意外な展開
ところが、1年ほどたったある日、思いがけない展開となる。「東京西徳洲会病院が療養病棟を立ち上げるため、ぜひ参加してほしい」と知人から打診を受けたのだ。
「徳洲会グループと言えば、急性期医療のイメージが強く、当初は私が行く場ではないように思いました。しかし、院内を見学して説明を聞くうちに気持ちが変わりました。急性期中心の病院であるだけに療養病棟専属の医師がおらず、診療がスムーズに回っていなかったのです」
康明会病院に残るかどうか迷ったが、自分を必要としているのはどちらか考えると、答えは自明だった。
「康明会病院はすでに高齢者医療をスムーズに行う体制が確立されており、私がいなくても診療は回ります。一方で、東京西徳洲会病院の療養病棟は今始まろうとしているところでした。自分にできることがあるなら、力になりたいと思ったのです」
AFTER 転職後
高齢者専門の療養型病院と
急性期病院の中にある療養病棟は
似ているようで大きく違う。」
療養病棟専属医として入職し病棟スタッフから感謝の声
東京西徳洲会病院の療養病棟は49床で、患者の約2割が急性期病棟からの転科。残り約8割は他病院からの紹介によって入院している。地域の高齢者にとって、地元の病院で療養できることは大きな支えだ。
2011年12月から病棟の準備が始まり、当初は急性期の医師や非常勤医がなんとか病棟を回してきた。しかし、専属の医師がいないことは病棟スタッフに負担がかかる。12年4月に瀧宮氏が入職すると、スタッフからは「医師がいつもいて指示を受けられるようになって安心した」と感謝の声があがった。
入職から丸2年がたった今、瀧宮氏が実感しているのは、高齢者医療専門の療養型病院と、急性期病院の中にある療養病棟との違いである。
「療養型病院であれば、高齢者に適した診療の流れを医師同士で共有できています。それに対し、当院の診療の流れは、急性期を中心として考えられています。しかし、感染症対策や、薬の選定、使い方などは、すべて急性期と同じ方法が高齢者医療に適しているとは限りません。また、治療後の検査や処置も、急性期と高齢者医療では異なる部分も少なくなく、適宜、自分で工夫しながら効率化する必要があります」
「人を診る」医療には多職種連携が不可欠

病棟スタッフと密なコミュニケーションを取りながら診療にあたる瀧宮氏。
瀧宮氏は、少しずつでも着実に、院内で療養病棟のポジショニングを確立することを目指している。
「療養病棟は、急性期の治療を終えた患者の行き先を的確に判断する場です。終身で入院するのか、自宅へ戻るのか、別の病院や介護施設へ移るのかなど選択肢はさまざまですが、患者の希望を叶えるには生活環境や家族関係、人生観、哲学なども把握しなくてはなりません。いわば『病気』ではなく『人』を診る医療です」
そうした医療を実践するために心がけているのは、病棟スタッフとの密なコミュニケーションだ。医師、看護師のみならず、介護職員、リハビリスタッフ、医療ソーシャルワーカー(MSW)も含めた多職種連携が欠かせないと言う。
「入院前の病歴はカルテや紹介状でわかりますが、生活歴や経済状況などはMSWの協力なくしては得られない情報です。医師のトップダウンではなく、みんなが同じ立場で目標を持って話し合うことが大切です」
時には、専門としている日本温泉気候物理医学会の情報をスタッフに伝えることもある。「温泉の効能などを学術的に研究している学会です。薬や手術では治らない高齢の患者には、有用な情報もあるのです」
誠実かつ、柔軟な姿勢を保っている瀧宮氏。「多職種が協力して、患者や家族の望む医療ができた時にやりがいを感じます」と語る笑顔には、高齢者医療に対する優しさがにじむ。
WELCOME
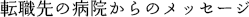
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 総長 板垣徹也氏
一度は閉鎖した療養病棟を地域の求めに応じて再開設
東京西徳洲会病院のある昭島市は、少し足を伸ばせば立川市や八王子市に行き当たり、二次医療圏では100万人の医療を担っている。総長の板垣徹也氏は、2005年の開院以降をこう振り返る。
「もともとは二つの療養病棟を持つ病院でした。07年にDPCを導入した際、急性期に特化するために一度は療養病棟を閉鎖したのですが、12年に再び開設しました。この辺りには療養病床が不足し、住民たちのニーズが高かったためです」
瀧宮氏が入職したのは、そのタイミングである。長年にわたって培ってきた高齢者医療の経験は、療養病棟で提供される医療の質を確実に高めている。
「瀧宮先生が来られてから、安定した病棟運営ができるようになりました。患者が入浴する頻度、介護との連携など、急性期の医師では気づかないところまで瀧宮先生は見てくださっています。そのためか、病棟スタッフたちの働く意欲も向上しています。また、急性期の治療を終えたあとに転院しなくても済むようになったことで、地域住民の安心感も増していると感じます」
徳洲会グループと言えば、急性期医療を力強くけん引するイメージがあるかもしれないが、あくまでも地域医療を守ることが前提である。板垣氏は「徳洲会グループは、地域に介護事業所や高齢者施設なども設け、地域の中で医療が回ることを大切にしています」と語る。
医師個人の意欲を組織として表現できる場
今後の同院の方針としては、がん治療などの専門医療と、救急総合医療を両立させること。加えて、先端医療への協力も惜しまない病院でありたいと、板垣氏は考えている。
「徳洲会グループは、常に新しい研究や治療にトライアルしながら成長してきました。以前は、ゲノム研究に積極的に検体を提供していましたが、今後はiPS細胞の研究に協力する方針です」
つまり、急性期で専門性を高めたい医師、瀧宮氏のように療養病棟で力を発揮したい医師、そして新しいことに挑戦したい医師のすべてにとって、活躍できるフィールドがあると言える。板垣氏は、若手医師に向けてこうアドバイスする。
「専門医志向を持つことは大事ですが、ずっと同じ領域を突き詰められる医師はわずかです。多くは、専門性の幅を広げるか、新しいことにチャレンジしてキャリアを切り開いています。私自身、もともと脳外科医ですが、離島やへき地医療も経験して現在は総合診療に携わっています。医師には多様な可能性があります。あまり専門性を狭め過ぎず、関心のあることに挑戦してほしいですね。当院は、そうした個人の意欲を、組織として表現できる場です」

- 板垣 徹也氏
- 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 総長
- 東京都出身。1971年京都大学医学部卒業。脳外科医として吉田病院、松江赤十字病院、兵庫医科大学病院、天理よろづ相談所病院を経て、83年福岡徳洲会病院に入職。その後、宇治徳洲会病院、名瀬徳洲会病院を経て2005年に東京西徳洲会病院に入職。
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院
2005年、徳洲会グループとして初めて東京都内に開院。小児から高齢者まで診療する地域基幹病院として地域住民に親しまれている。昭島市内には200床以上の病院が少ないため、月間救急搬入数は600件を超える。縦割りの診療科にとどまらず、診療科を横断するセンター化を実現。循環器センター、乳腺腫瘍センター、脊椎センターなど13領域のセンターを設けているのも特徴だ。

| 正式名称 | 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市松原町3-1-1 |
| 設立年月日 | 2005年9月1日 |
| 診療科目 | 内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、心臓血管外科、 消化器内科・外科、内視鏡外科、呼吸器科、神経内科、 肝臓内科、腎臓内科、外科、脳神経外科、 整形外科、脊椎外科、関節外科(スポーツ整形外科)、形成外科、 美容外科、泌尿器科(人工透析)、乳腺腫瘍科、小児科、 皮膚科、婦人科、歯科口腔外科、放射線科、 麻酔科(ペインクリニック)、病理科、リハビリテーション科、救急科 |
| 病床数 | 364床 |
| 常勤医師数 | 55名 |
| 非常勤医師数 | 35名 |
| 看護師数 | 210名 |
| 外来患者数 | 1日平均600人 |
| 入院患者数 | 1日平均250人(2014年3月末日現在) |
この記事を読んだ方におすすめ
- 希望にマッチした求人は?
- 一般内科の求人を探してみる
- 幅広く求人を検討したい方
- 非公開求人を紹介してもらう
- 転職全般 お悩みの方
- 転職のプロに相談してみる
※ご相談は無料です
実録・私のキャリアチェンジ一覧
医師の方々が、どんな想いを胸に転職に踏み切ったのか、転職前後の状況をお聞きしました。
-
- 自らの力を存分に発揮して「患者のための医療」を貫き地域医療の要となる存在に

- 羽生総合病院【循環器科】髙橋 暁行氏(53歳)
-
- 断らない救急医療を実践 他の診療科・病院との連携で患者の暮らし全体を支えていく

- 相澤病院【救急科】宮内 直人氏(34歳)
-
- 培った専門性を生かしながらワーク・ライフ・バランスも充実する矯正医療を選んだ

- 大阪医療刑務所【消化器外科】岡田 かおる氏(45歳)
-
- QOLの低下を防ぐ整形外科 人工関節置換術や関節鏡手術で地域の健康と幸せをサポート

- 浅草病院【整形外科】望月 義人氏(40歳)
-
- 専門医とも連携した体制で患者と家族が望む暮らしをかなえる在宅医療を提供

- 静岡ホームクリニック【内科】松本 拓也氏(40歳)
-
- 患者の期待に応える治療が続けられることを条件に転職し 肝がん治療で地域有数の病院に

- 渕野辺総合病院【内科】小池 幸宏氏(57歳)
-
- 診断がつかない患者を引き受け 適切な治療に導く総合診療で地域医療の質を向上させる

- 西東京中央総合病院【総合診療科】小河原 忠彦氏(63歳)
-
- 与えられた条件や環境の中で実現可能な治療を選択し在宅患者に適切な医療を提供

- 東大和病院附属セントラルクリニック【循環器内科】桑田 雅雄氏(59歳)
-
- 外来、入院、在宅、看取りまで 腎臓病の患者をトータルに診てその人らしい生き方を支援する

- 調布東山病院【腎臓内科】村岡 和彦氏(39歳)
-
- 一人ひとりの気持ちに寄り添い専門領域まで在宅でカバー 患者が満足する医療を目指す

- クリニック グリーングラス【内科】中村 喜亮氏(42歳)
-
- ESDなど内視鏡診断・治療のエキスパートがそろう病院で地域の先進的なニーズに応える

- メディカルトピア草加病院【消化器内科】吉田 智彦氏(40歳)
-
- 自らの将来を何度も問い直し循環器の専門性を極める道から総合的に診る内科のジェネラリストに

- 平塚市民病院【内科】片山 順平氏(39歳)
-
- 都心に近い中規模の病院で地域に高度な医療を提供 自分の成長も実感する毎日

- 新松戸中央総合病院【外科】竹内 瑞葵氏(30歳)
-
- 治療の初期から終末期まで充実した緩和ケアによりその人らしい生き方を支援

- 新生病院【緩和ケア内科・外科】森廣雅人氏(49歳)
-
- 形成外科、総合診療科を中心に地域に必要とされる医療を提供 褥瘡治療で患者のQOL向上を図る

- 郡山青藍病院【形成外科】中山毅一郎氏(44歳)
-
- 被収容者の健康管理と社会復帰を支援する矯正医官 医療の本質とも向き合う

- 府中刑務所医務部/法務省矯正局(併任)【外科】岩田 要氏(44歳)
-
- 産業医の経験も生かして患者の社会復帰・在宅復帰に力を尽くす

- 上越地域医療センター病院【総合診療科】岩崎 登氏(40歳)
-
- 外来、病棟、訪問診療まで地域医療を総合的に担う現場で患者を最期まで受け止める

- 横浜甦生病院【内科】建部 雄氏氏(48歳)
-
- WHO等での経験も活かして感染症危機管理の専門家に 検疫官としても日本の感染症対策に貢献

- 厚生労働省【医療専門職】井手一彦氏(42歳)
-
- 認知症の診療から病院運営まで多様な経験をすべて生かして地域の精神科医療を担う

- ホスピタル坂東【精神科】久永明人氏(53歳)
-
- 手外科の医師からリハビリ医に適切な回復期リハを提供し在宅療養を含む地域医療に貢献

- 平和台病院【リハビリテーション科】五十嵐康美氏(64歳)
-
- 医療過疎が進むエリアでも消化器分野の専門治療を提供 地域完結の医療を強化する

- 岡波総合病院【内科】今井 元氏(40歳)
-
- 100人の外務省医務官とともに在外邦人のメンタルケアを充実させ、海外での活躍を支援

- 外務省診療所【精神科】鈴木 満氏(63歳)
-
- 在宅医療支援から看取りまで患者と家族の両方に望まれる療養型の病院を実現したい

- シーサイド病院【内科】嘉数 徹氏(65歳)
-
- 短期間収容される被収容者の健康を適切に維持管理しスムーズな社会復帰を支援

- 京都拘置所 医務課診療所【内科】落合哲治氏(47歳)
-
- 脳神経外科の経験を生かし急性期から回復期リハまで地域医療に幅広く貢献する

- 新生病院【脳神経外科】鳥海勇人氏(52歳)
-
- 三次救急での経験を生かし市内唯一の総合病院で理想の二次救急医療を目指す

- 白岡中央総合病院【救急科】篠原克浩氏(51歳)
-
- 目の前の患者を救うやりがいと家族と過ごせる時間の両方を救急医療の最前線で手に入れた

- 総合大雄会病院【救命救急】竹村元太氏(34歳)
-
- 地域が求める婦人科へ 近隣の急性期病院と連携しがん治療の前と後を担う

- 共立蒲原総合病院【婦人科】伊吹 友二氏(53歳)
-
- 長年の救急医療の経験をもとに自分が理想としていた地域医療・高齢者医療を実現

- つばさ総合診療所【内科】八木啓一氏(64歳)
-
- 外来、入院、訪問診療と一人の患者を最期まで診ていく理想の地域医療が実現できた

- 共立病院【内科】重成憲爾氏(42歳)
-
- 内科の総合診療の力をもとに透析患者を丁寧に診るという自分の理想を実現できる職場

- 松山西病院【内科】藤岡英樹氏(53歳)
-
- 矯正施設からの社会復帰のため被収容者の心身の健康を支え地域への受け入れも進めたい

- 大阪医療刑務所【外科】加藤保之氏(66歳)
-
- 自ら心臓血管外科を立ち上げ地域の患者に本当に必要な高度医療を提供したい

- 羽生総合病院【心臓血管外科】平野智康氏(47歳)
-
- 患者の人生に寄り添って本人や家族が希望する医療を在宅のままで実現したい

- 大宮在宅クリニック【内科】清水章弘氏(32歳)
-
- ハンセン病の診療と並行して途上国の国際保健活動に従事 日本と世界をつなげる

- 国立駿河療養所【皮膚科】四津里英氏(38歳)
-
- 幅広い精神科医療により地域のニーズを満たす診療を行い自らも成長できる道を選んだ

- ハートランドしぎさん【精神科】山下圭一氏(33歳)
-
- 道南全域の急性期医療を担い、患者や家族、そして地域からも喜ばれる救急医の道を選んだ

- 函館五稜郭病院【集中治療センター(救急担当兼務)】小林 慎氏(58歳)
-
- 多様な診療経験をもとに患者の気持ちに寄り添い求められる医療を提供したい

- 上越地域医療センター病院【リハビリテーション科・緩和ケア科】渡辺俊雄氏(57歳)
-
- 患者がいるところが診療の場 自分が目指す地域医療は在宅診療の中にあった

- 三鷹あゆみクリニック【内科】山根秀章氏(36歳)
-
- 大腸内視鏡での高度な診断を地域に根ざした病院で幅広く役立てる道を選んだ

- 福岡輝栄会病院【消化器内科】鍋山健太郎氏(48歳)
-
- 回復期、療養、緩和ケアなどそれぞれに応じたリハビリで患者の在宅復帰を可能に

- 鶴巻温泉病院【内科】蓮江健一郎氏(46歳)
-
- 柔軟な働き方ができる矯正施設での診療を通して、被収容者の社会復帰を支援する

- 網走刑務所 医務課診療所【内科】大松広伸氏(54歳)
-
- 精神科病棟で多職種が協力し患者の社会復帰を目指す新たな医療が実践できる

- NTT東日本 伊豆病院【精神科】藤山 航氏(46歳)
-
- 他の医療機関とも連携してこれから地域が必要とする医療を提供していきたい

- 館林厚生病院【脳神経外科】高橋 潔氏(59歳)
-
- 乳がん治療から乳房再建まで患者の悩みを総合的に引き受ける医師になった

- 埼玉医科大学国際医療センター【乳腺腫瘍科・形成外科】廣川詠子氏(34歳)
-
- 自分の専門性を磨きながら地域密着の医療にも貢献 進むべき道は沖縄にあった

- 北部地区医師会病院【消化器内科】川又久永氏(51歳)
-
- 医局での経験、経営の知識、自分のすべてをぶつけて地域に必要な病院をつくる

- 宇和島徳洲会病院【循環器内科】池田佳広氏(42歳)
-
- 患者一人ひとりを丁寧に診て安心してもらえる医療を提供できる体制に満足

- 我孫子聖仁会病院【整形外科】石山典幸氏(45歳)
-
- 最先端のがん診療を行う病院で子育てと両立させて働ける健診センターの仕事を選んだ

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【健診センター検診部】山田由美氏(36歳)
-
- 不妊治療の第一線にいながら家庭も大切にできる理想の職場に巡り合った

- オーク住吉産婦人科【産科・婦人科】苅田正子氏(41歳)
-
- 家族と一緒に暮らしながら地域に根ざした診療ができるそんな環境を選んだ

- 玄々堂君津病院【消化器外科】久保田将氏(39歳)
-
- 科学的にも根拠のある認知行動療法で、患者の苦しみを和らげる診療を

- 山容病院【精神科】渋谷直史氏(34歳)
-
- Uターンで故郷の危機に直面。地域重視へと転換を図る病院で、治療の手応えを実感する

- 塩田記念病院【整形外科】石井薫氏(58歳)
-
- まだ命を救う現場にいたい。医療への思いから転身し、理想の医療現場を構築中

- 池上総合病院【外科】飛田浩輔氏(55歳)
-
- がん専門病院や大学病院で身につけた診療技術を地域医療に役立てる

- 共立蒲原総合病院【内科医長】横山ともみ氏(36歳)
-
- 「官」から「民」への転職。外科医としてのスキルを磨き、科の立ち上げや再構築にも関わる

- 白岡中央総合病院【外科部長】森田大作氏(47歳)
-
- 病気の社会的要因に興味を持ち、スウェーデンで社会学を学んだ。その知見を地域医療に生かす

- 健和会病院【内科】大槻朋子氏(41歳)
-
- 救急から整形外科へ――。医学部入学前からの計画をキャリアチェンジで実現する

- 角谷整形外科病院【整形外科】原田誠氏(34歳)
-
- 卒後10年目の決意。「形成外科医の少ない地域で住民の方々の役に立ちたい」

- 久喜総合病院【形成外科医長】信太薫氏(38歳)
-
- 外科の臨床に携わりつつ、副院長として病院経営にあたる。絶妙なバランスでキャリアを築く

- 佐々総合病院【外科医長】鈴木隆文氏(54歳)
-
- 子どもの頃から夢だった海外医療協力を実現し、日本での仕事、生活とも両立。

- 新生病院【整形外科医長】酒井典子氏(41歳)
-
- ずっと思い描いていた「将来の医師像」に近づくためキャリアチェンジに挑戦。

- 羽生総合病院【循環器科医長】鈴木 健司氏(44歳)
-
- 育児中もキャリアを中断させず、がん研有明病院に転職。社会に貢献できる医療に尽くす。

- 公益財団法人がん研究会がん研有明病院【乳腺外科】片岡明美氏(45歳)
-
- 定年を機に、急性期病院から高齢者中心の療養型病院へ。無理なく、やりがいある医療を追求。

- 総泉病院【内科】内田潤氏(62歳)
-
- 呼吸器内科医としての専門性を、地元の医療に生かしたい。その夢をかなえたキャリアチェンジ。

- 国際親善総合病院【呼吸器内科】中田裕介氏(42歳)
-
- 目指すは、どんな症例でも診られる”外科版のジェネラリスト”。豊富な症例で臨床スキルを磨く。

- 横浜旭中央総合病院【消化器外科】筋師健氏(34歳)
-
- 内視鏡のスペシャリストとして、市内最大の総合病院で活躍。消化器センターの新設に奔走する。

- 富士重工業健康保険組合 太田記念病院【消化器内科】大竹陽介氏(43歳)
-
- 尊敬する医師、信頼できる仲間と力を合わせながら、“攻めの二次救急”に挑戦する。

- 医療法人社団永生会 南多摩病院【救急科・循環器科部長】関裕氏(44歳)
-
- 世界トップレベルのクリニックで日進月歩で技術が進む不妊治療を学び、患者を救う。

- 医療法人 浅田レディースクリニック【婦人科】近藤麻奈美氏(33歳)
-
- 診療に打ち込みやすい病院を離れ、故郷・姫路にUターン。一から専門外科を立ち上げた。

- 医療法人松藤会入江病院【糖尿病内科】清水匡氏(43歳)
-
- 地域医療のやりがいと働きやすさを兼ね備えた環境で内科医としてのキャリアを築く。

- 国保多古中央病院【内科】中島賢一氏(48歳)
-
- 誰もが知っている大病院で技術を研き、国の乳がん治療の方向性にも関与する。

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【乳腺外科】坂井威彦氏(40歳)
-
- 大学病院を離れ、地域医療の最前線へ。日々、新たなやりがいを感じる。

- 医療法人三愛会 三愛会総合病院【眼科】伊藤正臣氏(40歳)
-
- ジェネラリストになるために東大を離れ、一般病院へ。診療の幅の広がりを実感する。

- 医療法人社団東山会 調布東山病院【糖尿病・内分泌内科】熊谷真義氏(36歳)
-
- “血液内科から訪問診療へ。穏やかな療養生活を支える役目に医師としての充実感がある。

- 医療法人社団めぐみ会田村クリニック【血液内科】安川清貴氏(44歳)
-
- 医局を離れ、一般病院へ。幼い頃に通った行徳総合病院で地域密着型の医療に貢献

- IMS(イムス)グループ医療法人財団明理会行徳総合病院【腎臓内科】青山 雅則氏(39歳)
-
- 高齢者医療に携わって20年。急性期病院の中の療養病棟で患者と家族の希望を叶える日々

- 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院【療養病棟】瀧宮顕彦氏(56歳)
-
- 自分の専門領域に集中でき、仲間と支え合える“理想郷”のような病院

- 医療法人福寿会メディカルトピア草加病院【婦人科】小堀宏之氏(43歳)
-
- 医療機器の充実した“夢のある病院”で、呼吸器外科の専門性を発揮

- パナソニック健康保険組合松下記念病院【呼吸器外科】和泉宏幸氏(43歳)
-
- 外科、緩和ケアを経験し、在宅診療で患者を看取るやりがいに気づいた。

- 医療法人社団八心会上田医院【在宅診療科】佐藤拓道氏(46歳)
-
- ”リハビリを学ぶ場”として最適の環境でスキルアップ。自分らしい医療を実現した。

- 医療法人社団永生会永生病院【リハビリテーション科】野本達哉氏(44歳)
-
- 病理医から精神科医へ。“直接患者の役に立つ喜び”を転職によって手に入れた。

- 特定医療法人寿栄会 有馬高原病院【精神科】畑中薫氏(70歳)
-
- 子どもの進学を機に長野から茨城の病院へ。100点満点の転職を果たした

- 医療法人茨城愛心会 古河病院 整形外科部長【整形外科】中村信幸氏(53歳)
-
- 母の死から立ち直れたのは周囲の支えがあったから。今は私が患者とその家族を守る。

- 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 後期研修医【総合内科】栗本美緒氏(27歳)
-
- 専門を備えた総合内科医になりたい。理想の環境で腕を磨きつつ次世代の医師育成にも励む日々

- 医療法人社団保健会 谷津保健病院 診療部長(兼)内科部長【内科】須藤真児氏(49歳)
-
- 妻に恥じず子供に誇れる、自分が理想とする医療を後進とともに追求したいと願った

- 公益財団法人 東京都医療保険協会 練馬総合病院 循環器内科【循環器内科】伊藤鹿島氏(39歳)
-
- 日本初の北米式研修システムと都市部では希少なER式救急を通じ診断学と教育に強く関与したい

- 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急部【救急科】舩越拓氏(32歳)
-
- 通勤時間を惜しむほどの激務から自宅まで徒歩2分の病院に転職私生活を大切にできる環境へ

- 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院【化学療法科】中村将人氏(39歳)
-
- 大学の医局には入らず慢性期・急性期ともに学べるスーパー救急のある病院へ一直線

- 社会医療法人公徳会 佐藤病院【神経科】加藤舞子氏(31歳)
-
- 脳梗塞患者の回復していく姿を間近でずっと見守りたい。医師として切実な願いだった

- 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院【神経内科】藤田聡志氏(32歳)
-
- 多様化する医師のキャリア――製薬企業で創薬に医師としての経験を活かしたい

- ヤンセンファーマ株式会社 研究開発本部医療法人和会 渋谷コアクリニック(非常勤勤務)【精神科】高橋長秀氏(37歳)
-
- 大学病院から一般病院への転身。「本当に学べる場」との出会いが麻酔科医としてスキル向上に導く

- 医療法人社団順江会 江東病院【麻酔科】大見貴秀氏(32歳)
-
- 若く、キャリアが短いからこそ斡旋会社を利用。プロの力に助けられて、幸せな転職を叶える。

- 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 泌尿器科【泌尿器科】木田智氏(29歳)





