VOL.73
他の医療機関とも連携して
これから地域が必要とする
医療を提供していきたい
館林厚生病院
脳神経外科 高橋 潔氏氏(59歳)
愛媛県出身
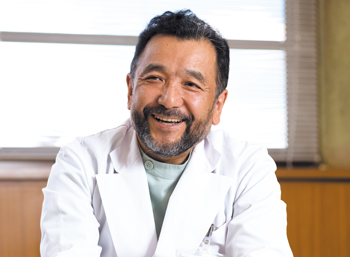
- 1981年
- 群馬大学医学部 卒業後、同学部附属病院 脳神経外科
- 1982年
- 伊勢崎市民病院 脳神経外科
- 1983年
- 国立東信病院(現:国立病院機構 信州上田医療センター)
脳神経外科 - 1983年
- 近森病院 脳神経外科
- 1984年
- 群馬大学医学部附属病院
脳神経外科・病理学第一講座(現:病態病理学) - 1986年
- 南東北病院(現:脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院)
脳神経外科 - 1986年
- 群馬大学医学部附属病院 脳神経外科
- 1988年
- 近森病院 脳神経外科 1991年より同科科長
- 1992年
- 佐久総合病院 脳神経外科(医長)
- 1993年
- 近森病院 脳神経外科(部長)
- 2014年
- 館林厚生病院 脳神経外科 入職 同部長に就任
26年も在籍した病院を辞して、57歳で新たな病院に。「この年齢から公務員になるとは思わなかった」と笑う高橋潔氏は、自治体が共同で設置主体となる公的総合病院、館林厚生病院に2014年に入職した。専門は脳神経外科だが、院内のクリニカルパスを再整備したり、地域で摂食嚥下の研究会を立ち上げたりと多彩な活動を続け、大きなやりがいを感じているという。
『リクルートドクターズキャリア』2017年5月号掲載
BEFORE 転職前
目の前にある命を救いたい
医療への思いを実現したくて
脳神経外科を選んだ
医師になったのは周囲の影響
脳神経外科は自分自身の夢
20年以上も高知県の病院で診療を続けていた高橋潔氏が、群馬県にある館林厚生病院に移ったのは57歳のとき。新天地でも以前と同じ脳神経外科を続けようと決めたのは、大学時代から抱く強い思いがあったためだという。
「私が医師を目指したのは母の勧めなど周囲の影響が強かったから。しかし自分が目標とする医師像は最初から非常に明確で、『目の前で倒れた人も救える医師になりたい』と強く思っていました」
当時の高橋氏の選択肢にあったのは脳神経外科か麻酔科。脳血管障害は一刻も早い治療が求められるが、そうした責任の重さをやりがいと受け止めたのだろう。先輩の勧誘も後押しとなり、高橋氏は脳神経外科を選んだ。
卒業後は群馬県や近県の病院を行き来して経験を積んだ高橋氏。
「私が行った病院は大学から離れた場所が多く、医局の指導がタイムリーに受けられない反面、早くから『何でも自分でやっていこう』といった自立心が養えたのはよかったと思っています」
最も長く勤務した病院との出会いは偶然から
そして数年が経った頃、高橋氏は専門医の取得を目指して、多くの症例が診られる病院に腰を落ち着けたいと考え始めた。
「その候補となった病院の中には高知県の近森病院も含まれていました。といっても最初は違う病院に行く予定でしたが……」
それまで近森病院にいた医師が都合で急に医局に戻ることになり、すぐ対応できる高橋氏に白羽の矢が立ったのだという。
「私は愛媛県出身で、同じ四国の高知県には親しみもありますし、非常に症例数も多い病院と聞いていたので即答でした」
近森病院は群馬大学の関連病院で、特に脳神経外科は1970年代から医師を派遣するなど縁は深い。高橋氏も1983年に初めて同院で診療した後、1988年から4年、1993年からは21年と、自らのキャリアの3分の2以上を過ごすことになった。
「いろいろな状況が重なり、自分の居場所が見つかったことに不思議なつながりを感じましたね」
障害が残る患者のためにも 地域との後方連携に注力
高橋氏は同院で診療を始めて数年で脳神経外科の科長となり、医長、部長を歴任。診療科のリーダーとして数多くの症例を扱い、手術を行い、後輩を育て上げた。
そうやって院内の診療にある程度納得できるようになった高橋氏が、次に目を向けたのは地域医療、特に患者が退院後に利用する施設等との後方連携だった。
「脳神経外科で治療を終え、命は助かったものの障害は残るような患者さんもいらっしゃいます。そうした方が医療施設や福祉施設で不安なく過ごせるよう、地域と関係を深めたいと考えました」
最初のうちは各施設と個別に情報交換をしていたが、同院で高橋氏を主体としたクリニカルパスの作成・導入が進み、その対象を地域にも広げることで、より効果的な連携につながっていった。
「クリニカルパス自体は院内向けで、多職種によるチーム医療が浸透して、各自の専門性を生かした連携が本格化するなど大きなメリットがありました。そして病院でどんな医療を行うのかが明確になることで、地域との連携もさらに深まっていったのです」
さらに高橋氏は脳卒中に特化した地域連携クリニカルパスの作成も主導し、脳神経外科で治療した患者が地域の施設でよりよい生活を送れるよう力を注いだという。
「また近隣の病院と合同でパスの発表大会を行ったり、高知県庁とのつながりもできたりと、地域の中での交流が広がりましたね」
このほか院内ではNSTの立ち上げを提案するなど、2000年頃から脳神経外科の枠に収まらない活動を続けてきた高橋氏。
「高知市内に自宅も建てましたし、このまま定年まで近森病院にいるのだろうと思っていました」
それが急転直下、慣れ親しんだ同院を去ることにしたのは、妻の希望があったためだという。
「高知県に来てずっと仕事中心の生活でしたから、今度は妻の気持ちを大切にしたかったのです」
AFTER 転職後
自分の診療だけでなく、
病院や地域の医療レベルを
向上させるために活動中
地域の救急ニーズに応え 脳血管などの救急医療に従事
30代から50代のほとんどを高知県で過ごし、その間は本当に仕事ばかりで妻には迷惑のかけ通しだったと振り返る高橋氏。
「しかし、娘夫婦に孫が生まれることになり、私の妻が子どもたちの近くに住んでサポートし、孫の世話をしたいと希望したのです」
自分の仕事も一段落ついたと感じていた高橋氏は病院と大学の医局を離れ、2014年に群馬県の館林厚生病院に入職した。
同院は自治体が共同で設置主体となった公的病院。地域のニーズに応えて救急医療にも力を入れ、高橋氏が責任者を務める脳神経外科と脳心血管センター、そして循環器内科が協力して脳血管や心血管の重篤な病気に対応する。
「救急車の受け入れも多いのですが、私自身が執刀する手術はなるべく減らして、当院では後進の育成に努めています」
こうした急性期医療以外にも同院は回復期リハビリ病棟、地域包括ケア病棟を持ち、患者に必要な診療を行っているのが特色だ。
また高橋氏は当時の院長と相談してクリニカルパス委員会を引き継ぎ、以前に同院が作成したパスを多職種連携、地域連携の視点から再整備も行っている。
「当院で整備したクリニカルパスは公開パス大会などを通じて医療関係者に情報提供し、地域を巻き込んだクリニカルパスへと発展させたいと考えています」
医療機関を越えて学び合う症例検討会を主催する
それまでいた民間病院と同院との違いを高橋氏はこう語る。
「規模も小さく、医師数も少ないなど院内の環境も違いましたが、公的病院だけあって、近隣の医療機関や施設に地域連携の話がしやすいのは実感しましたね。あの病院が地域のことを考えてくれるなら、とにかく話は聞こうと前向きな対応がほとんどでした」
高橋氏が主体となって始めた地域連携の一例が、医療機関を越えた症例検討会の実施だ。これは同院のある館林市のほか、桐生市や太田市など群馬県東部に勤務する脳神経外科医を集めて行うもの。
「当地区は群馬大学からの派遣が多いものの、勉強のためとはいえ大学まで頻繁に通える距離ではありません。ですから地域内での勉強会で知識を共有し、互いのレベルアップを図りたいのです」
医療・介護に携わる人材を 地域で育てる病院でありたい
また高橋氏は館林市、隣接する邑楽(おうら)町で「館林・邑楽おくちのリハビリ研究会」を立ち上げ、摂食嚥下障害についての勉強会もスタートさせている。
「脳卒中の治療後、嚥下障害でお困りの患者さんは多く、そうした障害から少しでも回復してもらいたいと思って、医療職や介護職に勉強の機会を提供しています」
この勉強会は年数回のペースで続いており、毎回100人程度が参加。第5回は2017年3月に開かれ、口腔ケアによる肺炎の予防がテーマだった。
「厚生労働省の『平成27年人口動態統計(確定数)』で、日本人の死亡原因3位となった肺炎を予防することは、今後の地域医療で重要な課題と考えています」
同院は地域医療支援病院でもあり、地域の医療・介護に携わる人材の育成も大事な使命の一つ。高橋氏はそう考えている。
このような活動を見ていると、高橋氏は好奇心旺盛で積極的にチャレンジするタイプに思える。
「そうでもありません(笑)。基本は引っ込み思案で、昔は自分から何か始めることは皆無でした」
自ら動く性格は脳神経外科の科長や医長の立場が作ったものと自己分析する高橋氏。今回のキャリアチェンジで地域連携を一層深めているのは、公的病院という立場が後押ししているに違いない。

同院で行われた公開クリニカルパス大会で発表する高橋氏。
WELCOME
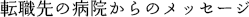
公的病院として地域が求める診療を行う
急性期から慢性期まで 地域医療に幅広く貢献
館林厚生病院は近隣6市町の自治体が設置主体となった病院。6市町には約18万人が住むが300床超の病院は同院だけで、唯一の公的総合病院として地域医療の拠り所となっている。
「当院でないと診られない救急の患者さんも多く、救急車は年間で約3500台、昼夜を問わず毎日10台前後は引き受けています」
地域の救急医療のニーズに応えることも公的病院の大切な使命だと院長の新井昌史氏はいう。
「二次救急までの対応ですが、心血管や脳血管の治療は医師数も充実しており、心筋梗塞や脳梗塞といった短時間での処置が求められる症例も得意としています」
また群馬県がん診療連携推進病院として、手術、放射線治療、薬物治療を適切に提供するなど、地域の中で三大疾病の治療を完結できるよう体制を整えている。
こうした急性期医療に加え、同院は48床の回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟も設け、回復期や慢性期までカバー。人間ドックなどの健診にも積極的だ。
「地域の健康を守る当院の診療内容は多種多様で、消化器外科で内視鏡を扱ったり、泌尿器科でIMRTのような高度な治療を取り入れたりと、希望すれば新たなチャレンジも可能なのです」
同院は群馬大学医学部、自治医科大学、獨協医科大学、埼玉医科大学などから同程度の距離にあり、医師の出身大学も幅広いという。
「学閥のない自由な気風のもとで、地域医療への貢献が実感できるのも魅力と感じています」
そうした環境の中で、脳神経外科部長兼脳心血管センター長を務める高橋氏は診療科のレベルアップはもちろん、病院全体の質の向上にも大いに貢献してくれていると新井氏は高く評価する。
「多職種や地域との密接な連携を前提としたクリニカルパスの再構築、栄養管理や嚥下訓練を行うNSTの強化などは、高橋先生が率先して取り組んでくれたおかげです。今後は高齢社会に必要な整形外科の充実など、各自治体とも協力して十分な対応を進めます」
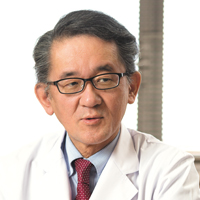
- 新井昌史氏
- 館林厚生病院 院長
- 1983年新潟大学医学部卒業後、群馬大学循環器・呼吸器内科(現:臓器病態内科学)に入局。1993年同医局で医学博士を取得。専門は心不全、分子循環器病学など。2014年から館林厚生病院に副院長として着任し、2015年に院長就任。地域包括センター長も兼務。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会循環器専門医。
館林厚生病院
同院のある館林市に加え、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町が共同で設立した邑楽(おうら)館林医療事務組合が設置主体。この地域に欠かせない公的総合病院として、二次救急、多様な診療科による外来および入院診療、健診など地域のニーズを幅広くカバーする。15年の新病院開院時に医療機器を一新。館林駅前のマンションと提携して医師の住環境を充実させるなど、働きやすさにも配慮している。

| 正式名称 | 邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市成島町262-1 |
| 設立年 | 1964年 |
| 診療科目 | 内科、精神科、循環器内科、 内分泌糖尿病内科、アレルギー呼吸器科、 小児科、外科、整形外科、形成外科、 脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、 消化器外科、皮膚科、泌尿器科、 産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、 リハビリテーション科、放射線診断科、 放射線治療科、歯科、歯科口腔外科 |
| 病床数 | 329床 (一般275床 感染6床 回復期48床) |
| 常勤医師数 | 39人 |
| 非常勤医師数 | 30人 |
| 外来患者数 | 377人/日 |
| 入院患者数 | 270人/日 |
| (2017年2月時点) |
この記事を読んだ方におすすめ
- 希望にマッチした求人は?
- 脳神経外科の求人を探してみる
- 幅広く求人を検討したい方
- 非公開求人を紹介してもらう
- 転職全般 お悩みの方
- 転職のプロに相談してみる
※ご相談は無料です
実録・私のキャリアチェンジ一覧
医師の方々が、どんな想いを胸に転職に踏み切ったのか、転職前後の状況をお聞きしました。
-
- 自らの力を存分に発揮して「患者のための医療」を貫き地域医療の要となる存在に

- 羽生総合病院【循環器科】髙橋 暁行氏(53歳)
-
- 断らない救急医療を実践 他の診療科・病院との連携で患者の暮らし全体を支えていく

- 相澤病院【救急科】宮内 直人氏(34歳)
-
- 培った専門性を生かしながらワーク・ライフ・バランスも充実する矯正医療を選んだ

- 大阪医療刑務所【消化器外科】岡田 かおる氏(45歳)
-
- QOLの低下を防ぐ整形外科 人工関節置換術や関節鏡手術で地域の健康と幸せをサポート

- 浅草病院【整形外科】望月 義人氏(40歳)
-
- 専門医とも連携した体制で患者と家族が望む暮らしをかなえる在宅医療を提供

- 静岡ホームクリニック【内科】松本 拓也氏(40歳)
-
- 患者の期待に応える治療が続けられることを条件に転職し 肝がん治療で地域有数の病院に

- 渕野辺総合病院【内科】小池 幸宏氏(57歳)
-
- 診断がつかない患者を引き受け 適切な治療に導く総合診療で地域医療の質を向上させる

- 西東京中央総合病院【総合診療科】小河原 忠彦氏(63歳)
-
- 与えられた条件や環境の中で実現可能な治療を選択し在宅患者に適切な医療を提供

- 東大和病院附属セントラルクリニック【循環器内科】桑田 雅雄氏(59歳)
-
- 外来、入院、在宅、看取りまで 腎臓病の患者をトータルに診てその人らしい生き方を支援する

- 調布東山病院【腎臓内科】村岡 和彦氏(39歳)
-
- 一人ひとりの気持ちに寄り添い専門領域まで在宅でカバー 患者が満足する医療を目指す

- クリニック グリーングラス【内科】中村 喜亮氏(42歳)
-
- ESDなど内視鏡診断・治療のエキスパートがそろう病院で地域の先進的なニーズに応える

- メディカルトピア草加病院【消化器内科】吉田 智彦氏(40歳)
-
- 自らの将来を何度も問い直し循環器の専門性を極める道から総合的に診る内科のジェネラリストに

- 平塚市民病院【内科】片山 順平氏(39歳)
-
- 都心に近い中規模の病院で地域に高度な医療を提供 自分の成長も実感する毎日

- 新松戸中央総合病院【外科】竹内 瑞葵氏(30歳)
-
- 治療の初期から終末期まで充実した緩和ケアによりその人らしい生き方を支援

- 新生病院【緩和ケア内科・外科】森廣雅人氏(49歳)
-
- 形成外科、総合診療科を中心に地域に必要とされる医療を提供 褥瘡治療で患者のQOL向上を図る

- 郡山青藍病院【形成外科】中山毅一郎氏(44歳)
-
- 被収容者の健康管理と社会復帰を支援する矯正医官 医療の本質とも向き合う

- 府中刑務所医務部/法務省矯正局(併任)【外科】岩田 要氏(44歳)
-
- 産業医の経験も生かして患者の社会復帰・在宅復帰に力を尽くす

- 上越地域医療センター病院【総合診療科】岩崎 登氏(40歳)
-
- 外来、病棟、訪問診療まで地域医療を総合的に担う現場で患者を最期まで受け止める

- 横浜甦生病院【内科】建部 雄氏氏(48歳)
-
- WHO等での経験も活かして感染症危機管理の専門家に 検疫官としても日本の感染症対策に貢献

- 厚生労働省【医療専門職】井手一彦氏(42歳)
-
- 認知症の診療から病院運営まで多様な経験をすべて生かして地域の精神科医療を担う

- ホスピタル坂東【精神科】久永明人氏(53歳)
-
- 手外科の医師からリハビリ医に適切な回復期リハを提供し在宅療養を含む地域医療に貢献

- 平和台病院【リハビリテーション科】五十嵐康美氏(64歳)
-
- 医療過疎が進むエリアでも消化器分野の専門治療を提供 地域完結の医療を強化する

- 岡波総合病院【内科】今井 元氏(40歳)
-
- 100人の外務省医務官とともに在外邦人のメンタルケアを充実させ、海外での活躍を支援

- 外務省診療所【精神科】鈴木 満氏(63歳)
-
- 在宅医療支援から看取りまで患者と家族の両方に望まれる療養型の病院を実現したい

- シーサイド病院【内科】嘉数 徹氏(65歳)
-
- 短期間収容される被収容者の健康を適切に維持管理しスムーズな社会復帰を支援

- 京都拘置所 医務課診療所【内科】落合哲治氏(47歳)
-
- 脳神経外科の経験を生かし急性期から回復期リハまで地域医療に幅広く貢献する

- 新生病院【脳神経外科】鳥海勇人氏(52歳)
-
- 三次救急での経験を生かし市内唯一の総合病院で理想の二次救急医療を目指す

- 白岡中央総合病院【救急科】篠原克浩氏(51歳)
-
- 目の前の患者を救うやりがいと家族と過ごせる時間の両方を救急医療の最前線で手に入れた

- 総合大雄会病院【救命救急】竹村元太氏(34歳)
-
- 地域が求める婦人科へ 近隣の急性期病院と連携しがん治療の前と後を担う

- 共立蒲原総合病院【婦人科】伊吹 友二氏(53歳)
-
- 長年の救急医療の経験をもとに自分が理想としていた地域医療・高齢者医療を実現

- つばさ総合診療所【内科】八木啓一氏(64歳)
-
- 外来、入院、訪問診療と一人の患者を最期まで診ていく理想の地域医療が実現できた

- 共立病院【内科】重成憲爾氏(42歳)
-
- 内科の総合診療の力をもとに透析患者を丁寧に診るという自分の理想を実現できる職場

- 松山西病院【内科】藤岡英樹氏(53歳)
-
- 矯正施設からの社会復帰のため被収容者の心身の健康を支え地域への受け入れも進めたい

- 大阪医療刑務所【外科】加藤保之氏(66歳)
-
- 自ら心臓血管外科を立ち上げ地域の患者に本当に必要な高度医療を提供したい

- 羽生総合病院【心臓血管外科】平野智康氏(47歳)
-
- 患者の人生に寄り添って本人や家族が希望する医療を在宅のままで実現したい

- 大宮在宅クリニック【内科】清水章弘氏(32歳)
-
- ハンセン病の診療と並行して途上国の国際保健活動に従事 日本と世界をつなげる

- 国立駿河療養所【皮膚科】四津里英氏(38歳)
-
- 幅広い精神科医療により地域のニーズを満たす診療を行い自らも成長できる道を選んだ

- ハートランドしぎさん【精神科】山下圭一氏(33歳)
-
- 道南全域の急性期医療を担い、患者や家族、そして地域からも喜ばれる救急医の道を選んだ

- 函館五稜郭病院【集中治療センター(救急担当兼務)】小林 慎氏(58歳)
-
- 多様な診療経験をもとに患者の気持ちに寄り添い求められる医療を提供したい

- 上越地域医療センター病院【リハビリテーション科・緩和ケア科】渡辺俊雄氏(57歳)
-
- 患者がいるところが診療の場 自分が目指す地域医療は在宅診療の中にあった

- 三鷹あゆみクリニック【内科】山根秀章氏(36歳)
-
- 大腸内視鏡での高度な診断を地域に根ざした病院で幅広く役立てる道を選んだ

- 福岡輝栄会病院【消化器内科】鍋山健太郎氏(48歳)
-
- 回復期、療養、緩和ケアなどそれぞれに応じたリハビリで患者の在宅復帰を可能に

- 鶴巻温泉病院【内科】蓮江健一郎氏(46歳)
-
- 柔軟な働き方ができる矯正施設での診療を通して、被収容者の社会復帰を支援する

- 網走刑務所 医務課診療所【内科】大松広伸氏(54歳)
-
- 精神科病棟で多職種が協力し患者の社会復帰を目指す新たな医療が実践できる

- NTT東日本 伊豆病院【精神科】藤山 航氏(46歳)
-
- 他の医療機関とも連携してこれから地域が必要とする医療を提供していきたい

- 館林厚生病院【脳神経外科】高橋 潔氏(59歳)
-
- 乳がん治療から乳房再建まで患者の悩みを総合的に引き受ける医師になった

- 埼玉医科大学国際医療センター【乳腺腫瘍科・形成外科】廣川詠子氏(34歳)
-
- 自分の専門性を磨きながら地域密着の医療にも貢献 進むべき道は沖縄にあった

- 北部地区医師会病院【消化器内科】川又久永氏(51歳)
-
- 医局での経験、経営の知識、自分のすべてをぶつけて地域に必要な病院をつくる

- 宇和島徳洲会病院【循環器内科】池田佳広氏(42歳)
-
- 患者一人ひとりを丁寧に診て安心してもらえる医療を提供できる体制に満足

- 我孫子聖仁会病院【整形外科】石山典幸氏(45歳)
-
- 最先端のがん診療を行う病院で子育てと両立させて働ける健診センターの仕事を選んだ

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【健診センター検診部】山田由美氏(36歳)
-
- 不妊治療の第一線にいながら家庭も大切にできる理想の職場に巡り合った

- オーク住吉産婦人科【産科・婦人科】苅田正子氏(41歳)
-
- 家族と一緒に暮らしながら地域に根ざした診療ができるそんな環境を選んだ

- 玄々堂君津病院【消化器外科】久保田将氏(39歳)
-
- 科学的にも根拠のある認知行動療法で、患者の苦しみを和らげる診療を

- 山容病院【精神科】渋谷直史氏(34歳)
-
- Uターンで故郷の危機に直面。地域重視へと転換を図る病院で、治療の手応えを実感する

- 塩田記念病院【整形外科】石井薫氏(58歳)
-
- まだ命を救う現場にいたい。医療への思いから転身し、理想の医療現場を構築中

- 池上総合病院【外科】飛田浩輔氏(55歳)
-
- がん専門病院や大学病院で身につけた診療技術を地域医療に役立てる

- 共立蒲原総合病院【内科医長】横山ともみ氏(36歳)
-
- 「官」から「民」への転職。外科医としてのスキルを磨き、科の立ち上げや再構築にも関わる

- 白岡中央総合病院【外科部長】森田大作氏(47歳)
-
- 病気の社会的要因に興味を持ち、スウェーデンで社会学を学んだ。その知見を地域医療に生かす

- 健和会病院【内科】大槻朋子氏(41歳)
-
- 救急から整形外科へ――。医学部入学前からの計画をキャリアチェンジで実現する

- 角谷整形外科病院【整形外科】原田誠氏(34歳)
-
- 卒後10年目の決意。「形成外科医の少ない地域で住民の方々の役に立ちたい」

- 久喜総合病院【形成外科医長】信太薫氏(38歳)
-
- 外科の臨床に携わりつつ、副院長として病院経営にあたる。絶妙なバランスでキャリアを築く

- 佐々総合病院【外科医長】鈴木隆文氏(54歳)
-
- 子どもの頃から夢だった海外医療協力を実現し、日本での仕事、生活とも両立。

- 新生病院【整形外科医長】酒井典子氏(41歳)
-
- ずっと思い描いていた「将来の医師像」に近づくためキャリアチェンジに挑戦。

- 羽生総合病院【循環器科医長】鈴木 健司氏(44歳)
-
- 育児中もキャリアを中断させず、がん研有明病院に転職。社会に貢献できる医療に尽くす。

- 公益財団法人がん研究会がん研有明病院【乳腺外科】片岡明美氏(45歳)
-
- 定年を機に、急性期病院から高齢者中心の療養型病院へ。無理なく、やりがいある医療を追求。

- 総泉病院【内科】内田潤氏(62歳)
-
- 呼吸器内科医としての専門性を、地元の医療に生かしたい。その夢をかなえたキャリアチェンジ。

- 国際親善総合病院【呼吸器内科】中田裕介氏(42歳)
-
- 目指すは、どんな症例でも診られる”外科版のジェネラリスト”。豊富な症例で臨床スキルを磨く。

- 横浜旭中央総合病院【消化器外科】筋師健氏(34歳)
-
- 内視鏡のスペシャリストとして、市内最大の総合病院で活躍。消化器センターの新設に奔走する。

- 富士重工業健康保険組合 太田記念病院【消化器内科】大竹陽介氏(43歳)
-
- 尊敬する医師、信頼できる仲間と力を合わせながら、“攻めの二次救急”に挑戦する。

- 医療法人社団永生会 南多摩病院【救急科・循環器科部長】関裕氏(44歳)
-
- 世界トップレベルのクリニックで日進月歩で技術が進む不妊治療を学び、患者を救う。

- 医療法人 浅田レディースクリニック【婦人科】近藤麻奈美氏(33歳)
-
- 診療に打ち込みやすい病院を離れ、故郷・姫路にUターン。一から専門外科を立ち上げた。

- 医療法人松藤会入江病院【糖尿病内科】清水匡氏(43歳)
-
- 地域医療のやりがいと働きやすさを兼ね備えた環境で内科医としてのキャリアを築く。

- 国保多古中央病院【内科】中島賢一氏(48歳)
-
- 誰もが知っている大病院で技術を研き、国の乳がん治療の方向性にも関与する。

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【乳腺外科】坂井威彦氏(40歳)
-
- 大学病院を離れ、地域医療の最前線へ。日々、新たなやりがいを感じる。

- 医療法人三愛会 三愛会総合病院【眼科】伊藤正臣氏(40歳)
-
- ジェネラリストになるために東大を離れ、一般病院へ。診療の幅の広がりを実感する。

- 医療法人社団東山会 調布東山病院【糖尿病・内分泌内科】熊谷真義氏(36歳)
-
- “血液内科から訪問診療へ。穏やかな療養生活を支える役目に医師としての充実感がある。

- 医療法人社団めぐみ会田村クリニック【血液内科】安川清貴氏(44歳)
-
- 医局を離れ、一般病院へ。幼い頃に通った行徳総合病院で地域密着型の医療に貢献

- IMS(イムス)グループ医療法人財団明理会行徳総合病院【腎臓内科】青山 雅則氏(39歳)
-
- 高齢者医療に携わって20年。急性期病院の中の療養病棟で患者と家族の希望を叶える日々

- 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院【療養病棟】瀧宮顕彦氏(56歳)
-
- 自分の専門領域に集中でき、仲間と支え合える“理想郷”のような病院

- 医療法人福寿会メディカルトピア草加病院【婦人科】小堀宏之氏(43歳)
-
- 医療機器の充実した“夢のある病院”で、呼吸器外科の専門性を発揮

- パナソニック健康保険組合松下記念病院【呼吸器外科】和泉宏幸氏(43歳)
-
- 外科、緩和ケアを経験し、在宅診療で患者を看取るやりがいに気づいた。

- 医療法人社団八心会上田医院【在宅診療科】佐藤拓道氏(46歳)
-
- ”リハビリを学ぶ場”として最適の環境でスキルアップ。自分らしい医療を実現した。

- 医療法人社団永生会永生病院【リハビリテーション科】野本達哉氏(44歳)
-
- 病理医から精神科医へ。“直接患者の役に立つ喜び”を転職によって手に入れた。

- 特定医療法人寿栄会 有馬高原病院【精神科】畑中薫氏(70歳)
-
- 子どもの進学を機に長野から茨城の病院へ。100点満点の転職を果たした

- 医療法人茨城愛心会 古河病院 整形外科部長【整形外科】中村信幸氏(53歳)
-
- 母の死から立ち直れたのは周囲の支えがあったから。今は私が患者とその家族を守る。

- 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 後期研修医【総合内科】栗本美緒氏(27歳)
-
- 専門を備えた総合内科医になりたい。理想の環境で腕を磨きつつ次世代の医師育成にも励む日々

- 医療法人社団保健会 谷津保健病院 診療部長(兼)内科部長【内科】須藤真児氏(49歳)
-
- 妻に恥じず子供に誇れる、自分が理想とする医療を後進とともに追求したいと願った

- 公益財団法人 東京都医療保険協会 練馬総合病院 循環器内科【循環器内科】伊藤鹿島氏(39歳)
-
- 日本初の北米式研修システムと都市部では希少なER式救急を通じ診断学と教育に強く関与したい

- 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急部【救急科】舩越拓氏(32歳)
-
- 通勤時間を惜しむほどの激務から自宅まで徒歩2分の病院に転職私生活を大切にできる環境へ

- 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院【化学療法科】中村将人氏(39歳)
-
- 大学の医局には入らず慢性期・急性期ともに学べるスーパー救急のある病院へ一直線

- 社会医療法人公徳会 佐藤病院【神経科】加藤舞子氏(31歳)
-
- 脳梗塞患者の回復していく姿を間近でずっと見守りたい。医師として切実な願いだった

- 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院【神経内科】藤田聡志氏(32歳)
-
- 多様化する医師のキャリア――製薬企業で創薬に医師としての経験を活かしたい

- ヤンセンファーマ株式会社 研究開発本部医療法人和会 渋谷コアクリニック(非常勤勤務)【精神科】高橋長秀氏(37歳)
-
- 大学病院から一般病院への転身。「本当に学べる場」との出会いが麻酔科医としてスキル向上に導く

- 医療法人社団順江会 江東病院【麻酔科】大見貴秀氏(32歳)
-
- 若く、キャリアが短いからこそ斡旋会社を利用。プロの力に助けられて、幸せな転職を叶える。

- 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 泌尿器科【泌尿器科】木田智氏(29歳)





