VOL.89
長年の救急医療の経験をもとに
自分が理想としていた
地域医療・高齢者医療を実現
つばさ総合診療所
内科 八木啓一氏(64歳)
大阪府出身

- 1981年
- 鳥取大学医学部卒業、大阪大学医学部附属病院 特殊救急部 入局
阪和記念病院 脳神経外科 - 1982年
- 愛知県厚生連海南病院 外科
- 1985年
- 大阪大学医学部附属病院 特殊救急部
- 1987年
- セントルイス大学(アメリカ) 麻酔科 research assistant professor
- 1990年
- 兵庫県立西宮病院 救急医療センター 医長
- 1992年
- 防衛医科大学校病院 救急部 助手(1993年から講師)
- 1996年
- 大阪府泉州救命救急センター 副所長
- 2000年
- 青梅市立総合病院 救命救急センター 部長(同年10月からセンター長兼務)
- 2002年
- 鳥取大学医学部 器官制御外科学救急・災害医学分野 教授
(2004年から救命救急センター長兼務) - 2009年
- 横浜市立みなと赤十字病院 救命救急センター センター長
(後に院長補佐、臨床教育センター長兼務) - 2018年
- つばさ総合診療所 入職
国内の救命救急センターの先駆けといわれる大阪大学医学部附属病院から、救急車による受入患者数が全国トップクラスの横浜市立みなと赤十字病院まで、八木啓一氏はキャリアのほとんどを救急医療に費やしてきた。しかし2018年に転職した八木氏は、「救急は自分がやりたい医療へと至るプロセスだった」と断言する。何を目指して医師になり、どのようなゴールにたどり着いたのか、その流れを追った。
『リクルートドクターズキャリア』2018年9月号掲載
BEFORE 転職前
地域の住民のために
何でも診られる医師を目指し、
選んだのは救急医療の道
診療所は町や村に1軒程度
医師は頼れる存在だった
医師として40年近いキャリアを持つ八木啓一氏は、国内の救命救急センターの先駆けといわれる大阪大学医学部附属病院特殊救急部に始まり、ほとんどを救急医療の最前線に身を投じてきた。そして2018年4月、自らの新たなキャリアとして選んだのがつばさ総合診療所(埼玉県)だ。
「もともと救急医療を目指したのは、どんな分野も診られる医師になって地域医療に貢献したかったから。長年の夢がかない、今は生き生きと仕事をしています」
そのような医師になろうと考えたのは、幼少期の暮らしが影響していると八木氏は振り返る。
「私の生まれは大阪府南西部でも特に人口が少ない地域で、当時は田畑の中に人家がぽつりぽつりといった感じ。診療所は町や村に1軒程度しかなく、医師はすべての患者を診るのが当たり前でした」
万一のときに頼れる存在だった医師に自然と憧れ、八木氏は医学部に入学。しかし医局選びはギリギリまで悩んだという。在学中に外科系に興味を持ち、最初は心臓血管外科への入局を考えたものの、自分が目指すような医師になるには、循環器を専門とするキャリアだけでは心細いと感じたからだ。
「全身を診るのなら小児科という道もあったのですが、あいにく私は子どもの扱いが苦手で(笑)。そうやって進路を選びかねているとき、私の同級生が救急医療に行くと聞いて、その道があったか!と目を開かれた思いでした」
施設の特性や院内連携により
救急医療は多様な面を見せる
最終的に八木氏が選んだのは大阪大学医学部附属病院。1967年に開設した特殊救急部は日本初の重症救急患者の専門施設として注目されていた。その頃の救急医療は交通外傷への対応が主だったため、入局後は関連病院と大学病院それぞれの外科で、半年ずつ研修するのが通例となっていた。
「当時の研修医は無給に近く、学生結婚をしていた私は妻にしばらく厄介をかけるな……と考えていました。ただ、関連病院のうち一つは多少なりとも給与が出ると聞き、研修希望の候補の一つに加えていたら、縁あってそこで研修を受けることになったのです」
いち早くCTを導入し、頭部外傷や脳腫瘍などを専門に治療する先進的な環境の中、八木氏は即戦力扱いで鍛えられたという。
その後は別の関連病院の外科、大学病院の特殊救急部、アメリカ留学を経て、兵庫県の病院で救急医療センター医長に就任。次に埼玉県の大学校病院で助手・講師を務め、自らの生まれ故郷に開設された救命救急センターで副所長となり、東京都下の病院では救命救急センターの立ち上げに加わるなど、さまざまな条件のもとで救急医療を実践してきた。
「しかし脳外科や心臓外科が充実した病院かそうでないかによって、脳梗塞や心筋梗塞の患者をどの程度の重症度まで救急で診るかは違ってきます。あるいは院内連携によって救急から各診療科への患者の受け渡しがスムーズだったり、妙に壁があったりと千差万別。それに30数年前は交通外傷が中心でしたが、今は高齢者が半数以上で、転倒によるけがや内科疾患も増えるなど、時代によっても救急医療は様変わりしています」
おかげで救急医療だけでも幅広い経験が積めた。八木氏は自らのキャリアをそう捉えている。
地方での救急医療に疲弊し
自分がやりたい道へと進んだ
さらに2002年から母校の救命救急センターで臨床と後進の教育に努めていた八木氏。臨床研修制度の変更は地方の救急医療に大きな痛手になったと付け加える。
「研修医は都市部に集中する傾向が強まり、地方の大学病院や関連病院に来る人員は激減。私はセンター長として医学部長や病院長と幾度も人員確保と勤務環境の改善を話し合いましたが、有効な改善策は打ち出せないままでした」
何年も精神的・体力的にギリギリの状態が続き、これが限界と感じた八木氏は部下とともに大学を退職。これは新聞やwebメディアにも大きく取り上げられた。
それから神奈川県の病院で救急医療に従事した後、八木氏は念願の地域医療の道へと進んだ。
AFTER 転職後
高齢者を一人ひとり丁寧に
診療するというゴールに
ようやくたどり着いた
救急医療と高齢者医療は
思った以上に似ている分野
八木氏が転職したつばさ総合診療所は主に高齢の患者を対象に、外来診療と介護施設などへの訪問診療・往診を行う医療施設。八木氏は昔から目指していたゴールにやっとたどり着けたと笑う。
「私にとっての医療の原点は、生まれ故郷の村にいた何でも診てくれる医師の姿なんです。特に高齢の患者さんを優しく診る姿が懐かしく、大学病院にいたときは救急医療の傍ら、高齢者医療の病院をアルバイト先に選んだほどです」
また近年は救急で運ばれてくる患者の半数以上は高齢者であり、八木氏にとって違和感がないどころか、この点を注意しないと容体が急変するといった知識がダイレクトに役立つ職場だという。
「また高齢になると複合疾患の患者さんも多く、全身を診てきた救急医の強みも生かせます」
生き生きと仕事をしているとの言葉通り、笑顔で語る八木氏。
「始めて数カ月ですが、おばあさんのファンも増えましたね(笑)」
主治医としての責任を持ち
患者ごとに適切な医療を提供
八木氏の一日は、診療所で当日診る患者の情報をもとにカルテを整理する業務から始まる。
「まだ受け持ったばかりで、ようやく患者さんの顔と名前を覚えたところですが、主治医として各自の病気と容体をしっかり把握し、薬の種類や量が適切かを確認するなど、やることは多いですね」
このため今はこうした準備に時間を取られると八木氏。患者はさまざまな医療機関を回り、そのときに出された薬を飲み続けている患者も目につくため、減薬を前提に患者ごとに適切な医療を提供できるようにしたいと話す。
八木氏が担当する患者の大半は施設入居者で、訪問診療が中心となっている。このため準備を終えると運転手、看護師などと訪問診療に出かけることがほとんど。訪問ペースは午前に1施設、午後に1施設で、施設で診療する患者数は15人ほど。1日に診る患者数は30人程度が平均的だ。
「夕方に診療所に戻って報告書をまとめたら業務終了。残業やオンコールはなく土日も確実に休めるので、救急にいた頃に比べるとストレスも感じませんね」
これからも仕事で成長し
同時に私生活も充実させたい
八木氏は救急医療の現場で自分が後輩に言い続けてきたことを、改めてかみしめているという。
「何でもすぐ検査に頼るのではなく、丁寧な視診・触診・問診で病気やけがの当たりをつけ、検査はあくまで確認など補助的に使うこと。これは一刻を争う救急医療や災害医療の基本ですが、訪問診療先で簡易的な検査機器を使って判断を下す際にも重要になります」
介護施設に親などを入居させているのは、家族の力だけではケアが難しいからだ。訪問診療では判断がつかないから、検査のため病院へ連れて行くようにといった指示は、そうした家族にとって非常な重荷になりかねない。
「このように救急医療でやってきたことにもっと磨きをかけ、新たな知識も吸収しながら、さらに成長を続けたいと考えています」
一方でプライベートはすでに大きく変わったと八木氏。趣味のランニングも、以前は夜中など時間が取れるときに走ってきたが、最近は早朝や土日など自分が気持ちいい時間帯に走れる。また好きな登山は転職後半年のうちに数回も行けるようになった。
「私は何事もやり過ぎる傾向があるようで、せっかく建てた自宅にも私は住むことなく、20年近く単身赴任を続けてきたのです。ここに来てようやく腰を落ち着けて、バランスのとれた人生が送れると実感しています」

訪問診療に出る前、診療所内で看護師と当日診る患者の容体などを再確認。
WELCOME
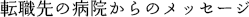
医療で高齢者と家族の幸せを支える
外来の整形外科・リハビリと
施設などへの在宅医療が中心
同診療所がある埼玉県入間市は東京都北西部と隣接するベッドタウンで、高齢化も着実に進展。そうした中、同診療所が担うのは地域の高齢者の外来診療と介護施設への訪問診療・往診などだ。
外来では一般内科のほか、特に整形外科や通所リハビリに力を入れ、患者や利用者の健康寿命の延伸に貢献。また在宅は介護施設の入居者や自宅療養の患者の健康管理が中心で、例えば内科なら在宅酸素療法や中心静脈栄養法(IVH)、経管栄養法、人工呼吸器の指導管理なども行っている。
また同診療所の場合、常勤医は当直やオンコールがなく、それらは専任の医師が担当。このためプライベートの時間をしっかり確保できるのも魅力となっている。
「ご家族による高齢者へのケアの一部を私たちが肩代わりし、ケアをする側もされる側も幸せになっていただく。そうした社会奉仕の仕事だと実感しています」
院長の坂口修平氏は診療の感想をこう語る。同氏も自らのクリニックを少し前に閉じ、同診療所に来た経歴を持つ。医療機器の維持・更新のコストに加え、高齢になるほど医療と経営の両面に責任を持つのは難しいと感じ、求められるうちに転職したという。
「私は内科の診療経験はあるものの、専門は形成外科・整形外科。長く救急医療で活躍していた八木先生の入職により、互いの強みを生かす体制を作ることができています。また患者さんやスタッフからも『話しやすい』と好評です」
ただそうしたバックグラウンドとは関係なく、患者と気持ちをつなげられる医師なら、相手の思いに寄り添う在宅医療で力を発揮できるはずと坂口氏は言い、自身は時間がかかっても患者の話をじっくり聞き、ことば遣いや態度も敬意を持って接していると話す。
「病気でなく患者さん自身を診る。在宅医療はそんな医師本来の姿に戻れる現場だと感じています。そして70歳になっても自分の力が求められ、患者さんやご家族に感謝してもらえる。そうした職場が見つかって私自身も幸せです」

- 坂口修平氏
- つばさ総合診療所 院長
- 1978年昭和大学医学部卒業後、同医学部形成外科に入局。首都圏を中心に大学病院・総合病院の整形外科、救命救急センター、形成外科などで経験を積む。1983年からパリ大学サン・ルイ病院形成外科に留学。1992年から父親経営のクリニックに加わり、後に継承。専門の形成外科のほか内科全般を診療する。2017年に同クリニックを閉院し、現職。
つばさ総合診療所
同診療所は首都圏を中心に外来医療・在宅医療事業、介護事業などを展開する医療法人グループの一員。内科および整形外科の外来診療、通所リハビリテーションに加え、併設の有料老人ホームや近隣の介護施設を対象に在宅医療を提供している。外来は予約制で常勤医と非常勤医で担当。現在は内科、整形外科を開設しており、高齢の患者を中心に、地域のかかりつけ医として総合的な健康の相談、足腰など関節の痛み・しびれなどに対応している。また理学療法士8人、作業療法士6人に加え、リハビリ助手、ヘルパーとスタッフが充実。在宅は内科のほか歯科、精神科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科と担当医師の専門分野を生かした体制を整えている。

| 正式名称 | 医療法人社団 白報会 つばさ総合診療所 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢350 |
| 開設年 | 2015年 |
| 診療科目 | 内科(外来・訪問)、整形外科(外来)、 歯科(訪問)、精神科(訪問)、眼科(訪問)、 皮膚科(訪問)、耳鼻咽喉科(訪問) |
| 常勤医師数 | 2人 |
| 非常勤医師数 | 4人 |
| 訪問診療担当患者数 | 270人(内科) |
| 訪問数 | 30人/日 |
| (2018年7月時点) |
この記事を読んだ方におすすめ
- 希望にマッチした求人は?
- 一般内科の求人を探してみる
- 幅広く求人を検討したい方
- 非公開求人を紹介してもらう
- 転職全般 お悩みの方
- 転職のプロに相談してみる
※ご相談は無料です
実録・私のキャリアチェンジ一覧
医師の方々が、どんな想いを胸に転職に踏み切ったのか、転職前後の状況をお聞きしました。
-
- 自らの力を存分に発揮して「患者のための医療」を貫き地域医療の要となる存在に

- 羽生総合病院【循環器科】髙橋 暁行氏(53歳)
-
- 断らない救急医療を実践 他の診療科・病院との連携で患者の暮らし全体を支えていく

- 相澤病院【救急科】宮内 直人氏(34歳)
-
- 培った専門性を生かしながらワーク・ライフ・バランスも充実する矯正医療を選んだ

- 大阪医療刑務所【消化器外科】岡田 かおる氏(45歳)
-
- QOLの低下を防ぐ整形外科 人工関節置換術や関節鏡手術で地域の健康と幸せをサポート

- 浅草病院【整形外科】望月 義人氏(40歳)
-
- 専門医とも連携した体制で患者と家族が望む暮らしをかなえる在宅医療を提供

- 静岡ホームクリニック【内科】松本 拓也氏(40歳)
-
- 患者の期待に応える治療が続けられることを条件に転職し 肝がん治療で地域有数の病院に

- 渕野辺総合病院【内科】小池 幸宏氏(57歳)
-
- 診断がつかない患者を引き受け 適切な治療に導く総合診療で地域医療の質を向上させる

- 西東京中央総合病院【総合診療科】小河原 忠彦氏(63歳)
-
- 与えられた条件や環境の中で実現可能な治療を選択し在宅患者に適切な医療を提供

- 東大和病院附属セントラルクリニック【循環器内科】桑田 雅雄氏(59歳)
-
- 外来、入院、在宅、看取りまで 腎臓病の患者をトータルに診てその人らしい生き方を支援する

- 調布東山病院【腎臓内科】村岡 和彦氏(39歳)
-
- 一人ひとりの気持ちに寄り添い専門領域まで在宅でカバー 患者が満足する医療を目指す

- クリニック グリーングラス【内科】中村 喜亮氏(42歳)
-
- ESDなど内視鏡診断・治療のエキスパートがそろう病院で地域の先進的なニーズに応える

- メディカルトピア草加病院【消化器内科】吉田 智彦氏(40歳)
-
- 自らの将来を何度も問い直し循環器の専門性を極める道から総合的に診る内科のジェネラリストに

- 平塚市民病院【内科】片山 順平氏(39歳)
-
- 都心に近い中規模の病院で地域に高度な医療を提供 自分の成長も実感する毎日

- 新松戸中央総合病院【外科】竹内 瑞葵氏(30歳)
-
- 治療の初期から終末期まで充実した緩和ケアによりその人らしい生き方を支援

- 新生病院【緩和ケア内科・外科】森廣雅人氏(49歳)
-
- 形成外科、総合診療科を中心に地域に必要とされる医療を提供 褥瘡治療で患者のQOL向上を図る

- 郡山青藍病院【形成外科】中山毅一郎氏(44歳)
-
- 被収容者の健康管理と社会復帰を支援する矯正医官 医療の本質とも向き合う

- 府中刑務所医務部/法務省矯正局(併任)【外科】岩田 要氏(44歳)
-
- 産業医の経験も生かして患者の社会復帰・在宅復帰に力を尽くす

- 上越地域医療センター病院【総合診療科】岩崎 登氏(40歳)
-
- 外来、病棟、訪問診療まで地域医療を総合的に担う現場で患者を最期まで受け止める

- 横浜甦生病院【内科】建部 雄氏氏(48歳)
-
- WHO等での経験も活かして感染症危機管理の専門家に 検疫官としても日本の感染症対策に貢献

- 厚生労働省【医療専門職】井手一彦氏(42歳)
-
- 認知症の診療から病院運営まで多様な経験をすべて生かして地域の精神科医療を担う

- ホスピタル坂東【精神科】久永明人氏(53歳)
-
- 手外科の医師からリハビリ医に適切な回復期リハを提供し在宅療養を含む地域医療に貢献

- 平和台病院【リハビリテーション科】五十嵐康美氏(64歳)
-
- 医療過疎が進むエリアでも消化器分野の専門治療を提供 地域完結の医療を強化する

- 岡波総合病院【内科】今井 元氏(40歳)
-
- 100人の外務省医務官とともに在外邦人のメンタルケアを充実させ、海外での活躍を支援

- 外務省診療所【精神科】鈴木 満氏(63歳)
-
- 在宅医療支援から看取りまで患者と家族の両方に望まれる療養型の病院を実現したい

- シーサイド病院【内科】嘉数 徹氏(65歳)
-
- 短期間収容される被収容者の健康を適切に維持管理しスムーズな社会復帰を支援

- 京都拘置所 医務課診療所【内科】落合哲治氏(47歳)
-
- 脳神経外科の経験を生かし急性期から回復期リハまで地域医療に幅広く貢献する

- 新生病院【脳神経外科】鳥海勇人氏(52歳)
-
- 三次救急での経験を生かし市内唯一の総合病院で理想の二次救急医療を目指す

- 白岡中央総合病院【救急科】篠原克浩氏(51歳)
-
- 目の前の患者を救うやりがいと家族と過ごせる時間の両方を救急医療の最前線で手に入れた

- 総合大雄会病院【救命救急】竹村元太氏(34歳)
-
- 地域が求める婦人科へ 近隣の急性期病院と連携しがん治療の前と後を担う

- 共立蒲原総合病院【婦人科】伊吹 友二氏(53歳)
-
- 長年の救急医療の経験をもとに自分が理想としていた地域医療・高齢者医療を実現

- つばさ総合診療所【内科】八木啓一氏(64歳)
-
- 外来、入院、訪問診療と一人の患者を最期まで診ていく理想の地域医療が実現できた

- 共立病院【内科】重成憲爾氏(42歳)
-
- 内科の総合診療の力をもとに透析患者を丁寧に診るという自分の理想を実現できる職場

- 松山西病院【内科】藤岡英樹氏(53歳)
-
- 矯正施設からの社会復帰のため被収容者の心身の健康を支え地域への受け入れも進めたい

- 大阪医療刑務所【外科】加藤保之氏(66歳)
-
- 自ら心臓血管外科を立ち上げ地域の患者に本当に必要な高度医療を提供したい

- 羽生総合病院【心臓血管外科】平野智康氏(47歳)
-
- 患者の人生に寄り添って本人や家族が希望する医療を在宅のままで実現したい

- 大宮在宅クリニック【内科】清水章弘氏(32歳)
-
- ハンセン病の診療と並行して途上国の国際保健活動に従事 日本と世界をつなげる

- 国立駿河療養所【皮膚科】四津里英氏(38歳)
-
- 幅広い精神科医療により地域のニーズを満たす診療を行い自らも成長できる道を選んだ

- ハートランドしぎさん【精神科】山下圭一氏(33歳)
-
- 道南全域の急性期医療を担い、患者や家族、そして地域からも喜ばれる救急医の道を選んだ

- 函館五稜郭病院【集中治療センター(救急担当兼務)】小林 慎氏(58歳)
-
- 多様な診療経験をもとに患者の気持ちに寄り添い求められる医療を提供したい

- 上越地域医療センター病院【リハビリテーション科・緩和ケア科】渡辺俊雄氏(57歳)
-
- 患者がいるところが診療の場 自分が目指す地域医療は在宅診療の中にあった

- 三鷹あゆみクリニック【内科】山根秀章氏(36歳)
-
- 大腸内視鏡での高度な診断を地域に根ざした病院で幅広く役立てる道を選んだ

- 福岡輝栄会病院【消化器内科】鍋山健太郎氏(48歳)
-
- 回復期、療養、緩和ケアなどそれぞれに応じたリハビリで患者の在宅復帰を可能に

- 鶴巻温泉病院【内科】蓮江健一郎氏(46歳)
-
- 柔軟な働き方ができる矯正施設での診療を通して、被収容者の社会復帰を支援する

- 網走刑務所 医務課診療所【内科】大松広伸氏(54歳)
-
- 精神科病棟で多職種が協力し患者の社会復帰を目指す新たな医療が実践できる

- NTT東日本 伊豆病院【精神科】藤山 航氏(46歳)
-
- 他の医療機関とも連携してこれから地域が必要とする医療を提供していきたい

- 館林厚生病院【脳神経外科】高橋 潔氏(59歳)
-
- 乳がん治療から乳房再建まで患者の悩みを総合的に引き受ける医師になった

- 埼玉医科大学国際医療センター【乳腺腫瘍科・形成外科】廣川詠子氏(34歳)
-
- 自分の専門性を磨きながら地域密着の医療にも貢献 進むべき道は沖縄にあった

- 北部地区医師会病院【消化器内科】川又久永氏(51歳)
-
- 医局での経験、経営の知識、自分のすべてをぶつけて地域に必要な病院をつくる

- 宇和島徳洲会病院【循環器内科】池田佳広氏(42歳)
-
- 患者一人ひとりを丁寧に診て安心してもらえる医療を提供できる体制に満足

- 我孫子聖仁会病院【整形外科】石山典幸氏(45歳)
-
- 最先端のがん診療を行う病院で子育てと両立させて働ける健診センターの仕事を選んだ

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【健診センター検診部】山田由美氏(36歳)
-
- 不妊治療の第一線にいながら家庭も大切にできる理想の職場に巡り合った

- オーク住吉産婦人科【産科・婦人科】苅田正子氏(41歳)
-
- 家族と一緒に暮らしながら地域に根ざした診療ができるそんな環境を選んだ

- 玄々堂君津病院【消化器外科】久保田将氏(39歳)
-
- 科学的にも根拠のある認知行動療法で、患者の苦しみを和らげる診療を

- 山容病院【精神科】渋谷直史氏(34歳)
-
- Uターンで故郷の危機に直面。地域重視へと転換を図る病院で、治療の手応えを実感する

- 塩田記念病院【整形外科】石井薫氏(58歳)
-
- まだ命を救う現場にいたい。医療への思いから転身し、理想の医療現場を構築中

- 池上総合病院【外科】飛田浩輔氏(55歳)
-
- がん専門病院や大学病院で身につけた診療技術を地域医療に役立てる

- 共立蒲原総合病院【内科医長】横山ともみ氏(36歳)
-
- 「官」から「民」への転職。外科医としてのスキルを磨き、科の立ち上げや再構築にも関わる

- 白岡中央総合病院【外科部長】森田大作氏(47歳)
-
- 病気の社会的要因に興味を持ち、スウェーデンで社会学を学んだ。その知見を地域医療に生かす

- 健和会病院【内科】大槻朋子氏(41歳)
-
- 救急から整形外科へ――。医学部入学前からの計画をキャリアチェンジで実現する

- 角谷整形外科病院【整形外科】原田誠氏(34歳)
-
- 卒後10年目の決意。「形成外科医の少ない地域で住民の方々の役に立ちたい」

- 久喜総合病院【形成外科医長】信太薫氏(38歳)
-
- 外科の臨床に携わりつつ、副院長として病院経営にあたる。絶妙なバランスでキャリアを築く

- 佐々総合病院【外科医長】鈴木隆文氏(54歳)
-
- 子どもの頃から夢だった海外医療協力を実現し、日本での仕事、生活とも両立。

- 新生病院【整形外科医長】酒井典子氏(41歳)
-
- ずっと思い描いていた「将来の医師像」に近づくためキャリアチェンジに挑戦。

- 羽生総合病院【循環器科医長】鈴木 健司氏(44歳)
-
- 育児中もキャリアを中断させず、がん研有明病院に転職。社会に貢献できる医療に尽くす。

- 公益財団法人がん研究会がん研有明病院【乳腺外科】片岡明美氏(45歳)
-
- 定年を機に、急性期病院から高齢者中心の療養型病院へ。無理なく、やりがいある医療を追求。

- 総泉病院【内科】内田潤氏(62歳)
-
- 呼吸器内科医としての専門性を、地元の医療に生かしたい。その夢をかなえたキャリアチェンジ。

- 国際親善総合病院【呼吸器内科】中田裕介氏(42歳)
-
- 目指すは、どんな症例でも診られる”外科版のジェネラリスト”。豊富な症例で臨床スキルを磨く。

- 横浜旭中央総合病院【消化器外科】筋師健氏(34歳)
-
- 内視鏡のスペシャリストとして、市内最大の総合病院で活躍。消化器センターの新設に奔走する。

- 富士重工業健康保険組合 太田記念病院【消化器内科】大竹陽介氏(43歳)
-
- 尊敬する医師、信頼できる仲間と力を合わせながら、“攻めの二次救急”に挑戦する。

- 医療法人社団永生会 南多摩病院【救急科・循環器科部長】関裕氏(44歳)
-
- 世界トップレベルのクリニックで日進月歩で技術が進む不妊治療を学び、患者を救う。

- 医療法人 浅田レディースクリニック【婦人科】近藤麻奈美氏(33歳)
-
- 診療に打ち込みやすい病院を離れ、故郷・姫路にUターン。一から専門外科を立ち上げた。

- 医療法人松藤会入江病院【糖尿病内科】清水匡氏(43歳)
-
- 地域医療のやりがいと働きやすさを兼ね備えた環境で内科医としてのキャリアを築く。

- 国保多古中央病院【内科】中島賢一氏(48歳)
-
- 誰もが知っている大病院で技術を研き、国の乳がん治療の方向性にも関与する。

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【乳腺外科】坂井威彦氏(40歳)
-
- 大学病院を離れ、地域医療の最前線へ。日々、新たなやりがいを感じる。

- 医療法人三愛会 三愛会総合病院【眼科】伊藤正臣氏(40歳)
-
- ジェネラリストになるために東大を離れ、一般病院へ。診療の幅の広がりを実感する。

- 医療法人社団東山会 調布東山病院【糖尿病・内分泌内科】熊谷真義氏(36歳)
-
- “血液内科から訪問診療へ。穏やかな療養生活を支える役目に医師としての充実感がある。

- 医療法人社団めぐみ会田村クリニック【血液内科】安川清貴氏(44歳)
-
- 医局を離れ、一般病院へ。幼い頃に通った行徳総合病院で地域密着型の医療に貢献

- IMS(イムス)グループ医療法人財団明理会行徳総合病院【腎臓内科】青山 雅則氏(39歳)
-
- 高齢者医療に携わって20年。急性期病院の中の療養病棟で患者と家族の希望を叶える日々

- 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院【療養病棟】瀧宮顕彦氏(56歳)
-
- 自分の専門領域に集中でき、仲間と支え合える“理想郷”のような病院

- 医療法人福寿会メディカルトピア草加病院【婦人科】小堀宏之氏(43歳)
-
- 医療機器の充実した“夢のある病院”で、呼吸器外科の専門性を発揮

- パナソニック健康保険組合松下記念病院【呼吸器外科】和泉宏幸氏(43歳)
-
- 外科、緩和ケアを経験し、在宅診療で患者を看取るやりがいに気づいた。

- 医療法人社団八心会上田医院【在宅診療科】佐藤拓道氏(46歳)
-
- ”リハビリを学ぶ場”として最適の環境でスキルアップ。自分らしい医療を実現した。

- 医療法人社団永生会永生病院【リハビリテーション科】野本達哉氏(44歳)
-
- 病理医から精神科医へ。“直接患者の役に立つ喜び”を転職によって手に入れた。

- 特定医療法人寿栄会 有馬高原病院【精神科】畑中薫氏(70歳)
-
- 子どもの進学を機に長野から茨城の病院へ。100点満点の転職を果たした

- 医療法人茨城愛心会 古河病院 整形外科部長【整形外科】中村信幸氏(53歳)
-
- 母の死から立ち直れたのは周囲の支えがあったから。今は私が患者とその家族を守る。

- 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 後期研修医【総合内科】栗本美緒氏(27歳)
-
- 専門を備えた総合内科医になりたい。理想の環境で腕を磨きつつ次世代の医師育成にも励む日々

- 医療法人社団保健会 谷津保健病院 診療部長(兼)内科部長【内科】須藤真児氏(49歳)
-
- 妻に恥じず子供に誇れる、自分が理想とする医療を後進とともに追求したいと願った

- 公益財団法人 東京都医療保険協会 練馬総合病院 循環器内科【循環器内科】伊藤鹿島氏(39歳)
-
- 日本初の北米式研修システムと都市部では希少なER式救急を通じ診断学と教育に強く関与したい

- 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急部【救急科】舩越拓氏(32歳)
-
- 通勤時間を惜しむほどの激務から自宅まで徒歩2分の病院に転職私生活を大切にできる環境へ

- 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院【化学療法科】中村将人氏(39歳)
-
- 大学の医局には入らず慢性期・急性期ともに学べるスーパー救急のある病院へ一直線

- 社会医療法人公徳会 佐藤病院【神経科】加藤舞子氏(31歳)
-
- 脳梗塞患者の回復していく姿を間近でずっと見守りたい。医師として切実な願いだった

- 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院【神経内科】藤田聡志氏(32歳)
-
- 多様化する医師のキャリア――製薬企業で創薬に医師としての経験を活かしたい

- ヤンセンファーマ株式会社 研究開発本部医療法人和会 渋谷コアクリニック(非常勤勤務)【精神科】高橋長秀氏(37歳)
-
- 大学病院から一般病院への転身。「本当に学べる場」との出会いが麻酔科医としてスキル向上に導く

- 医療法人社団順江会 江東病院【麻酔科】大見貴秀氏(32歳)
-
- 若く、キャリアが短いからこそ斡旋会社を利用。プロの力に助けられて、幸せな転職を叶える。

- 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 泌尿器科【泌尿器科】木田智氏(29歳)





