VOL.83
ハンセン病の診療と並行して
途上国の国際保健活動に従事
日本と世界をつなげる
国立駿河療養所
皮膚科 四津里英氏(38歳)
東京都出身

- 2004年
- 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業
聖路加国際病院 初期研修医 - 2006年
- 聖路加国際病院 皮膚科専門レジデント
- 2007年
- Liverpool School of Tropical Medicine, Master of International Public Health(イギリス)修了
- 2008年
- ALERT(All Africa Leprosy, Tuberculosis and Rehabilitation Training Centre)(エチオピア)研修修了
国立療養所 奄美和光園 医師 - 2009年
- 国立国際医療研究センター病院 皮膚科
- 2012年
- Gorgas Course in Clinical Tropical Medicine, Expert Course(ペルー)修了
Global Leprosy Programme, World Health Organization(インド)研修 - 2013年
- 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻修了
- 2014年
- Liverpool School of Tropical Medicine, Diploma in Tropical Medicine and Hygiene(イギリス)修了
国立駿河療養所 皮膚科 入職
国立駿河療養所でハンセン病による入所者を診ている四津里英(よつ・りえ)氏だが、ハンセン病について深く知るきっかけとなったのは海外で受けた研修からだという。ハンセン病を通して、「次第に自分が専門とする皮膚科と、興味があった国際保健分野がうまくつながっていった」と四津氏。自分がやりたいことは何かを常に探し続け、迷いながらもそれが実現できる道を選んできた四津氏の軌跡を追った。
『リクルートドクターズキャリア』2018年3月号掲載
BEFORE 転職前
自分の力で診断できる
プライマリーな医療を求めて
皮膚科を専門に選んだ
最初から海外で活躍できる
医師を目指していた
四津里英氏は2014年に国立駿河療養所(静岡県)に入職。ハンセン病による入所者の診療のほか、国内外の研究機関と連携して皮膚疾患の研究を続け、また発展途上国ではハンセン病をはじめ多様な皮膚疾患の調査・治療に取り組むなど、多方面で活躍している。
医師を目指したのは「人の役に立つ職業に就きたい」との思いから。また父親の仕事で小学3年生から中学卒業までアメリカで過ごした経験から、国際的な分野への興味も昔からあったという。
「入学した慈恵会医科大学は長い歴史を持つ伝統校でしたが、少人数での討議形式など新たな教育制度の導入にも積極的で、同じ目的を持つ学生同士の一体感もあって学びやすかったですね」
四津氏はこうした大学の授業や実習に加え、長期の休みにはアメリカで医学英語の教育プログラムを受講するなど、海外で活動するための準備も進めていった。
「しかも当時は医学部6年生になると、自分が興味のある病院で4カ月間の研修を受けられる機会があったのです。私はイギリス、アメリカ、フランスを回り、最先端医療を学んできました」
外科の高度医療から方向転換
皮膚科の診療に興味を持つ
四津氏の卒業時はちょうど現在の臨床研修制度が始まる時期だったが、その初期研修先に選んだのは聖路加国際病院だった。
「国際色豊かで、以前からスーパーローテートに近い研修を実施していた点も安心感がありました」
研修前の四津氏は「医師としてスキルを持って働く、そして人の役に立つには外科か産婦人科ではないか」といった漠然としたものだった。しかし医療現場では手術だけで治しきれないケースも多く、また高度な医療はときに一人の人間を人間として診られない不安を感じるときもあったという。
「思い描いていた医療はこういうものだったのかと問い直し、高度医療でなくプライマリーな医療に従事したいと、専門分野を再考したのが初期研修2年目でした」
そうした中で四津氏は皮膚科に興味を持ち始めた。大がかりな検査をしなくても、ある程度の疾患は自分の知識で診断がつくところも魅力で、母校の教えである「病気を診ずして病人を診よ」にもマッチするように思えたという。
さらに目標だった海外も先進国より途上国の状況を見たいと考え、病院長に相談。特例として初期研修終了後の6週間、ガーナでの臨床ボランティアに従事できた。
「現地で感じたのは、困難な状況で診療を続ける医師の力には限りがあり、支援するシステム構築や教育が必要ということでした。そこでもっとマクロな視点から国際保健を学ぼうと思ったのです」
一方、「国際保健の分野で働くにしても専門性が必要」と聖路加国際病院の皮膚科医長の助言により、帰国後、四津氏は当施設で皮膚科医としての道も歩みはじめる。しばらくしてイギリスで国際保健を学ぶ機会を得て渡英し、修了後はエチオピアで感染症に関する短期研修にも参加した。
「そのとき感染症、特にハンセン病について詳しく知り、私の専門である皮膚科と国際保健との接点を見つけることができました」
専門医取得と並行して
国内のハンセン病診療も経験
四津氏は合計1年数カ月の留学を終え、次に皮膚科の専門医取得を目指して日本へ帰国。国立国際医療研究センター病院の皮膚科という国際保健を学ぶ環境にも恵まれた最適な職場が見つかった。同院で診療を始めた直後、奄美大島のハンセン病療養所での研修を勧められたという。四津氏にとっても思いがけない話であった。
「半年間でしたが、受け入れ先に皮膚科の指導医もいて、いい経験になると考えて引き受けました。療養所は長期間入所されている方がほとんどで、ハンセン病も完治しており、いわば小さな村で地域医療に従事する感じでした」
半年間の研修を終え、四津氏は病院に戻って診療を続け専門医を取得。さらに海外でハンセン病など皮膚疾患の研究活動が増えていく中で、もう一度国内でハンセン病の診療を経験したいと考えるようになり、転職を決意した。
AFTER 転職後
ハンセン病による入所者が
安心して暮らせるよう
生活全般をケアしていく
国内でハンセン病を診る
機会は今しかないと考えた
四津氏が現在勤務している国立駿河療養所は、以前に研修で訪れた奄美大島の療養所と同じ国立ハンセン病療養所の一つ。国内の新規患者は現在ごくわずかで、同施設の入所者も減少を続けている。ハンセン病はほぼ完治し、後遺症や高齢化などのため入所を続けているケースがほとんどだ。
「あと十数年後には、国内でハンセン病を診る機会はほぼなくなります。私が療養所に転職したのは、半年間で終えた研修を中途半端に感じたこと。また、世界の現場に行くときに日本人として日本の現場も知っていることは重要。今のうちに国内でハンセン病とその後遺症の診療を経験しようと考えたからです」
さらに所長の福島一雄氏との相談で、国立国際医療研究センター病院での研究の継続、海外出張も認められ、療養所での診療以外に、ハンセン病をはじめとする熱帯皮膚感染症の研究、現地の調査・治療と幅広く活動している。
末梢神経障害で傷が絶えない
入所者をチーム力でケアする
ハンセン病にかかり治療が遅れると、末梢神経障害による知覚麻痺の後遺症が残ることが多い。このため手足をぶつけたり傷ついたりしてもわからず、常に傷が絶えず、治りにくい状態が続く。
四津氏は糖尿病患者の足潰瘍の治療も専門にしており、この経験を療養所で役立て、入所者の四肢の傷の治療にあたる。一方で、ハンセン病から学ぶことも多い。
「皮膚科医としてそうした傷の治療はもちろん、傷の予防についても考えなくてはなりません。幸い当施設には義肢装具士も常駐しているため、随時、足底板や装具を調整して傷の部分にかかる圧力を軽減するなどの措置を行っています。これは新たな傷を予防するためにも重要なケアのひとつです」
ほかにも看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのスタッフと気軽に話し合える環境で、入所者の診療やケアにチームとしてあたることができると四津氏。
「しかし入所者の平均年齢は約84歳と非常に高齢化し、施設内での看取りも行われています。大変な時代を生きてきた方たちに対し、ご本人が納得のいく最期をどう迎えていただくのかも重要な課題」
その準備として、四津氏は入所者一人ひとりのリビングウイルを記録し、保管しておく書類のフォーマットを作成。希望者に対して順次聞き取りを行っている。
海外で皮膚感染症の
診断と治療にも取り組む
このような国内状況と異なり、WHOが2016年に「ハンセン病の世界戦略2016-2020:ハンセン病のない世界への加速」を開始するなど、海外では一定数のハンセン病の感染が続いている。そのため四津氏はWHOや財団法人と協力。海外でハンセン病のほかさまざまな皮膚感染症の調査・研究に携わっている。
2014年に始まった「コートジボワール(西アフリカ)における学童皮膚検診」では、現地の学校で子どもたちを診断し、熱帯病による皮膚疾患の早期発見・早期治療に取り組んでいるという。
「最初は疫学的な調査から着手しましたが、今後は病気の診断ツールの開発、治療法の改善なども検討したいと考えています」
四津氏らが中心となって始めたこの調査も最初は小さな活動だったが、現在では世界的なムーブメントになりつつあるそうだ。
「それまであまり注目されていなかった分野に自分なりのアイデアを持ち込み、新たな可能性を見いだしていくのが私のやり方。まずは実践してみて、積み重ねることで、世界で認めてもらえると実感しています」

四津氏が国際保健活動の一つとして取り組んでいるコートジボワールでの学童皮膚検診。
WELCOME
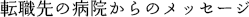
ハンセン病を全人的に診療する
病気による後遺症に加え
高齢者特有の疾患も診療
国立駿河療養所は第二次世界大戦中、南方でハンセン病に罹患して帰国した傷痍軍人を収容するための施設を母体とし、すでに70年超の歴史を有している。
「国立ハンセン病療養所は全国13カ所に置かれていますが、当施設より東には東京都下までなく、西は岡山県と離れており、東海北陸地区で唯一の療養所です」
そう語るのは熊本県の療養所で内科医長を務め、同施設への異動後に副所長を経て所長となった福島一雄氏。ハンセン病は感染力が弱い上、現代では多剤併用療法による治療法が確立され、すでに治療可能な病気となった。しかし有効な治療法がなかった時代に発症した患者は、完治後も後遺症に苦しんでいるケースが多いという。
「後遺症の一つに四肢の末梢部の知覚麻痺がありますが、これにより、やけどやけがに気づかず放置して悪化したり、感染症になったりするほか、視覚障がいが残ったりと日常生活に深刻な影響が出ている入所者の方は多いのです」
現在、56人の入所者全員が65歳以上と高齢。同施設はハンセン病の治療、後遺症に起因する外傷の治療、長く社会から離れて暮らす入所者に対するメンタルケアに加え、高齢者疾患も診る高齢重複障害者医療施設の役割も担っている。このため各診療科の医師やスタッフが協力して総合的な診療を提供していると福島氏。
「その中でも皮膚疾患や手足の傷の治療、傷を負わないよう保護カバーを装着するなど、皮膚科医の役目は重要で、四津先生を常勤医に迎えられて本当によかったと思っています。ハンセン病治療にも詳しく、国際保健分野の第一線でも活躍されていますから、新たな知識の共有にも期待しています」
また同施設では入所者の意向を尊重し、医療や介護を一定レベルに維持するなどを条件に、2015年から一般患者の診療を行って地域貢献をさらに進めている。
「当施設には緩和ケアで高いスキルを有する人材もいますから、今後はそうした分野で地域に活用されることも目指しています」
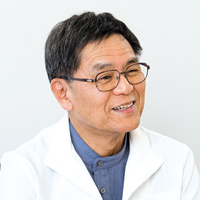
- 福島一雄氏
- 国立駿河療養所 所長
- 1979年熊本大学医学部卒業後、同第一内科(現:呼吸器内科)入局。1987年同大学院医学研究科(現:医学教育部)修了。結核予防会結核研究所病理学研究科、国立療養所再春荘病院(現:独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院)を経て、2006年国立療養所菊池恵楓園内科医長。2011年に国立駿河療養所副所長に就任、2014年から現職。日本呼吸器学会指導医・専門医、日本結核病学会結核・抗酸菌症指導医など。
国立駿河療養所
同施設は全国に13カ所ある国立ハンセン病療養所の一つで、富士山を望む約37万㎡の広大な敷地に、外来診療および入院治療を行う医療施設、入所者住居・医療ケア施設、入所者サービス部門などを持つ。入所者は1956年に471人となった以降は次第に減り、現在は56人。平均年齢は約84歳、全員が65歳以上の高齢者となっている。同院の医療・介護等は主に入所者に対して提供され、ハンセン病とその後遺症、高齢者疾患を中心に診療を行っている。常勤医による内科、外科、皮膚科、歯科に加え、非常勤医が眼科、耳鼻咽喉科、心療内科、整形外科までカバーし、スタッフは看護師や薬剤師のほか、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、義肢装具士などが常駐。マルチスライスCTも備え、検査体制の充実も図っている。

| 正式名称 | 国立駿河療養所 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県御殿場市神山1915 |
| 設立年 | 1945年 |
| 診療科目 | 内科 外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科 |
| 病床数 | 医療法病床数258床(一般258床) 入院定床 41床 |
| 常勤医師数 | 5人 |
| 非常勤医師数 | 19人 |
| 入院患者数 | 56人 |
| (2017年12月時点) |
この記事を読んだ方におすすめ
- 希望にマッチした求人は?
- 皮膚科の求人を探してみる
- 幅広く求人を検討したい方
- 非公開求人を紹介してもらう
- 転職全般 お悩みの方
- 転職のプロに相談してみる
※ご相談は無料です
実録・私のキャリアチェンジ一覧
医師の方々が、どんな想いを胸に転職に踏み切ったのか、転職前後の状況をお聞きしました。
-
- 自らの力を存分に発揮して「患者のための医療」を貫き地域医療の要となる存在に

- 羽生総合病院【循環器科】髙橋 暁行氏(53歳)
-
- 断らない救急医療を実践 他の診療科・病院との連携で患者の暮らし全体を支えていく

- 相澤病院【救急科】宮内 直人氏(34歳)
-
- 培った専門性を生かしながらワーク・ライフ・バランスも充実する矯正医療を選んだ

- 大阪医療刑務所【消化器外科】岡田 かおる氏(45歳)
-
- QOLの低下を防ぐ整形外科 人工関節置換術や関節鏡手術で地域の健康と幸せをサポート

- 浅草病院【整形外科】望月 義人氏(40歳)
-
- 専門医とも連携した体制で患者と家族が望む暮らしをかなえる在宅医療を提供

- 静岡ホームクリニック【内科】松本 拓也氏(40歳)
-
- 患者の期待に応える治療が続けられることを条件に転職し 肝がん治療で地域有数の病院に

- 渕野辺総合病院【内科】小池 幸宏氏(57歳)
-
- 診断がつかない患者を引き受け 適切な治療に導く総合診療で地域医療の質を向上させる

- 西東京中央総合病院【総合診療科】小河原 忠彦氏(63歳)
-
- 与えられた条件や環境の中で実現可能な治療を選択し在宅患者に適切な医療を提供

- 東大和病院附属セントラルクリニック【循環器内科】桑田 雅雄氏(59歳)
-
- 外来、入院、在宅、看取りまで 腎臓病の患者をトータルに診てその人らしい生き方を支援する

- 調布東山病院【腎臓内科】村岡 和彦氏(39歳)
-
- 一人ひとりの気持ちに寄り添い専門領域まで在宅でカバー 患者が満足する医療を目指す

- クリニック グリーングラス【内科】中村 喜亮氏(42歳)
-
- ESDなど内視鏡診断・治療のエキスパートがそろう病院で地域の先進的なニーズに応える

- メディカルトピア草加病院【消化器内科】吉田 智彦氏(40歳)
-
- 自らの将来を何度も問い直し循環器の専門性を極める道から総合的に診る内科のジェネラリストに

- 平塚市民病院【内科】片山 順平氏(39歳)
-
- 都心に近い中規模の病院で地域に高度な医療を提供 自分の成長も実感する毎日

- 新松戸中央総合病院【外科】竹内 瑞葵氏(30歳)
-
- 治療の初期から終末期まで充実した緩和ケアによりその人らしい生き方を支援

- 新生病院【緩和ケア内科・外科】森廣雅人氏(49歳)
-
- 形成外科、総合診療科を中心に地域に必要とされる医療を提供 褥瘡治療で患者のQOL向上を図る

- 郡山青藍病院【形成外科】中山毅一郎氏(44歳)
-
- 被収容者の健康管理と社会復帰を支援する矯正医官 医療の本質とも向き合う

- 府中刑務所医務部/法務省矯正局(併任)【外科】岩田 要氏(44歳)
-
- 産業医の経験も生かして患者の社会復帰・在宅復帰に力を尽くす

- 上越地域医療センター病院【総合診療科】岩崎 登氏(40歳)
-
- 外来、病棟、訪問診療まで地域医療を総合的に担う現場で患者を最期まで受け止める

- 横浜甦生病院【内科】建部 雄氏氏(48歳)
-
- WHO等での経験も活かして感染症危機管理の専門家に 検疫官としても日本の感染症対策に貢献

- 厚生労働省【医療専門職】井手一彦氏(42歳)
-
- 認知症の診療から病院運営まで多様な経験をすべて生かして地域の精神科医療を担う

- ホスピタル坂東【精神科】久永明人氏(53歳)
-
- 手外科の医師からリハビリ医に適切な回復期リハを提供し在宅療養を含む地域医療に貢献

- 平和台病院【リハビリテーション科】五十嵐康美氏(64歳)
-
- 医療過疎が進むエリアでも消化器分野の専門治療を提供 地域完結の医療を強化する

- 岡波総合病院【内科】今井 元氏(40歳)
-
- 100人の外務省医務官とともに在外邦人のメンタルケアを充実させ、海外での活躍を支援

- 外務省診療所【精神科】鈴木 満氏(63歳)
-
- 在宅医療支援から看取りまで患者と家族の両方に望まれる療養型の病院を実現したい

- シーサイド病院【内科】嘉数 徹氏(65歳)
-
- 短期間収容される被収容者の健康を適切に維持管理しスムーズな社会復帰を支援

- 京都拘置所 医務課診療所【内科】落合哲治氏(47歳)
-
- 脳神経外科の経験を生かし急性期から回復期リハまで地域医療に幅広く貢献する

- 新生病院【脳神経外科】鳥海勇人氏(52歳)
-
- 三次救急での経験を生かし市内唯一の総合病院で理想の二次救急医療を目指す

- 白岡中央総合病院【救急科】篠原克浩氏(51歳)
-
- 目の前の患者を救うやりがいと家族と過ごせる時間の両方を救急医療の最前線で手に入れた

- 総合大雄会病院【救命救急】竹村元太氏(34歳)
-
- 地域が求める婦人科へ 近隣の急性期病院と連携しがん治療の前と後を担う

- 共立蒲原総合病院【婦人科】伊吹 友二氏(53歳)
-
- 長年の救急医療の経験をもとに自分が理想としていた地域医療・高齢者医療を実現

- つばさ総合診療所【内科】八木啓一氏(64歳)
-
- 外来、入院、訪問診療と一人の患者を最期まで診ていく理想の地域医療が実現できた

- 共立病院【内科】重成憲爾氏(42歳)
-
- 内科の総合診療の力をもとに透析患者を丁寧に診るという自分の理想を実現できる職場

- 松山西病院【内科】藤岡英樹氏(53歳)
-
- 矯正施設からの社会復帰のため被収容者の心身の健康を支え地域への受け入れも進めたい

- 大阪医療刑務所【外科】加藤保之氏(66歳)
-
- 自ら心臓血管外科を立ち上げ地域の患者に本当に必要な高度医療を提供したい

- 羽生総合病院【心臓血管外科】平野智康氏(47歳)
-
- 患者の人生に寄り添って本人や家族が希望する医療を在宅のままで実現したい

- 大宮在宅クリニック【内科】清水章弘氏(32歳)
-
- ハンセン病の診療と並行して途上国の国際保健活動に従事 日本と世界をつなげる

- 国立駿河療養所【皮膚科】四津里英氏(38歳)
-
- 幅広い精神科医療により地域のニーズを満たす診療を行い自らも成長できる道を選んだ

- ハートランドしぎさん【精神科】山下圭一氏(33歳)
-
- 道南全域の急性期医療を担い、患者や家族、そして地域からも喜ばれる救急医の道を選んだ

- 函館五稜郭病院【集中治療センター(救急担当兼務)】小林 慎氏(58歳)
-
- 多様な診療経験をもとに患者の気持ちに寄り添い求められる医療を提供したい

- 上越地域医療センター病院【リハビリテーション科・緩和ケア科】渡辺俊雄氏(57歳)
-
- 患者がいるところが診療の場 自分が目指す地域医療は在宅診療の中にあった

- 三鷹あゆみクリニック【内科】山根秀章氏(36歳)
-
- 大腸内視鏡での高度な診断を地域に根ざした病院で幅広く役立てる道を選んだ

- 福岡輝栄会病院【消化器内科】鍋山健太郎氏(48歳)
-
- 回復期、療養、緩和ケアなどそれぞれに応じたリハビリで患者の在宅復帰を可能に

- 鶴巻温泉病院【内科】蓮江健一郎氏(46歳)
-
- 柔軟な働き方ができる矯正施設での診療を通して、被収容者の社会復帰を支援する

- 網走刑務所 医務課診療所【内科】大松広伸氏(54歳)
-
- 精神科病棟で多職種が協力し患者の社会復帰を目指す新たな医療が実践できる

- NTT東日本 伊豆病院【精神科】藤山 航氏(46歳)
-
- 他の医療機関とも連携してこれから地域が必要とする医療を提供していきたい

- 館林厚生病院【脳神経外科】高橋 潔氏(59歳)
-
- 乳がん治療から乳房再建まで患者の悩みを総合的に引き受ける医師になった

- 埼玉医科大学国際医療センター【乳腺腫瘍科・形成外科】廣川詠子氏(34歳)
-
- 自分の専門性を磨きながら地域密着の医療にも貢献 進むべき道は沖縄にあった

- 北部地区医師会病院【消化器内科】川又久永氏(51歳)
-
- 医局での経験、経営の知識、自分のすべてをぶつけて地域に必要な病院をつくる

- 宇和島徳洲会病院【循環器内科】池田佳広氏(42歳)
-
- 患者一人ひとりを丁寧に診て安心してもらえる医療を提供できる体制に満足

- 我孫子聖仁会病院【整形外科】石山典幸氏(45歳)
-
- 最先端のがん診療を行う病院で子育てと両立させて働ける健診センターの仕事を選んだ

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【健診センター検診部】山田由美氏(36歳)
-
- 不妊治療の第一線にいながら家庭も大切にできる理想の職場に巡り合った

- オーク住吉産婦人科【産科・婦人科】苅田正子氏(41歳)
-
- 家族と一緒に暮らしながら地域に根ざした診療ができるそんな環境を選んだ

- 玄々堂君津病院【消化器外科】久保田将氏(39歳)
-
- 科学的にも根拠のある認知行動療法で、患者の苦しみを和らげる診療を

- 山容病院【精神科】渋谷直史氏(34歳)
-
- Uターンで故郷の危機に直面。地域重視へと転換を図る病院で、治療の手応えを実感する

- 塩田記念病院【整形外科】石井薫氏(58歳)
-
- まだ命を救う現場にいたい。医療への思いから転身し、理想の医療現場を構築中

- 池上総合病院【外科】飛田浩輔氏(55歳)
-
- がん専門病院や大学病院で身につけた診療技術を地域医療に役立てる

- 共立蒲原総合病院【内科医長】横山ともみ氏(36歳)
-
- 「官」から「民」への転職。外科医としてのスキルを磨き、科の立ち上げや再構築にも関わる

- 白岡中央総合病院【外科部長】森田大作氏(47歳)
-
- 病気の社会的要因に興味を持ち、スウェーデンで社会学を学んだ。その知見を地域医療に生かす

- 健和会病院【内科】大槻朋子氏(41歳)
-
- 救急から整形外科へ――。医学部入学前からの計画をキャリアチェンジで実現する

- 角谷整形外科病院【整形外科】原田誠氏(34歳)
-
- 卒後10年目の決意。「形成外科医の少ない地域で住民の方々の役に立ちたい」

- 久喜総合病院【形成外科医長】信太薫氏(38歳)
-
- 外科の臨床に携わりつつ、副院長として病院経営にあたる。絶妙なバランスでキャリアを築く

- 佐々総合病院【外科医長】鈴木隆文氏(54歳)
-
- 子どもの頃から夢だった海外医療協力を実現し、日本での仕事、生活とも両立。

- 新生病院【整形外科医長】酒井典子氏(41歳)
-
- ずっと思い描いていた「将来の医師像」に近づくためキャリアチェンジに挑戦。

- 羽生総合病院【循環器科医長】鈴木 健司氏(44歳)
-
- 育児中もキャリアを中断させず、がん研有明病院に転職。社会に貢献できる医療に尽くす。

- 公益財団法人がん研究会がん研有明病院【乳腺外科】片岡明美氏(45歳)
-
- 定年を機に、急性期病院から高齢者中心の療養型病院へ。無理なく、やりがいある医療を追求。

- 総泉病院【内科】内田潤氏(62歳)
-
- 呼吸器内科医としての専門性を、地元の医療に生かしたい。その夢をかなえたキャリアチェンジ。

- 国際親善総合病院【呼吸器内科】中田裕介氏(42歳)
-
- 目指すは、どんな症例でも診られる”外科版のジェネラリスト”。豊富な症例で臨床スキルを磨く。

- 横浜旭中央総合病院【消化器外科】筋師健氏(34歳)
-
- 内視鏡のスペシャリストとして、市内最大の総合病院で活躍。消化器センターの新設に奔走する。

- 富士重工業健康保険組合 太田記念病院【消化器内科】大竹陽介氏(43歳)
-
- 尊敬する医師、信頼できる仲間と力を合わせながら、“攻めの二次救急”に挑戦する。

- 医療法人社団永生会 南多摩病院【救急科・循環器科部長】関裕氏(44歳)
-
- 世界トップレベルのクリニックで日進月歩で技術が進む不妊治療を学び、患者を救う。

- 医療法人 浅田レディースクリニック【婦人科】近藤麻奈美氏(33歳)
-
- 診療に打ち込みやすい病院を離れ、故郷・姫路にUターン。一から専門外科を立ち上げた。

- 医療法人松藤会入江病院【糖尿病内科】清水匡氏(43歳)
-
- 地域医療のやりがいと働きやすさを兼ね備えた環境で内科医としてのキャリアを築く。

- 国保多古中央病院【内科】中島賢一氏(48歳)
-
- 誰もが知っている大病院で技術を研き、国の乳がん治療の方向性にも関与する。

- 公益財団法人がん研究会 がん研有明病院【乳腺外科】坂井威彦氏(40歳)
-
- 大学病院を離れ、地域医療の最前線へ。日々、新たなやりがいを感じる。

- 医療法人三愛会 三愛会総合病院【眼科】伊藤正臣氏(40歳)
-
- ジェネラリストになるために東大を離れ、一般病院へ。診療の幅の広がりを実感する。

- 医療法人社団東山会 調布東山病院【糖尿病・内分泌内科】熊谷真義氏(36歳)
-
- “血液内科から訪問診療へ。穏やかな療養生活を支える役目に医師としての充実感がある。

- 医療法人社団めぐみ会田村クリニック【血液内科】安川清貴氏(44歳)
-
- 医局を離れ、一般病院へ。幼い頃に通った行徳総合病院で地域密着型の医療に貢献

- IMS(イムス)グループ医療法人財団明理会行徳総合病院【腎臓内科】青山 雅則氏(39歳)
-
- 高齢者医療に携わって20年。急性期病院の中の療養病棟で患者と家族の希望を叶える日々

- 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院【療養病棟】瀧宮顕彦氏(56歳)
-
- 自分の専門領域に集中でき、仲間と支え合える“理想郷”のような病院

- 医療法人福寿会メディカルトピア草加病院【婦人科】小堀宏之氏(43歳)
-
- 医療機器の充実した“夢のある病院”で、呼吸器外科の専門性を発揮

- パナソニック健康保険組合松下記念病院【呼吸器外科】和泉宏幸氏(43歳)
-
- 外科、緩和ケアを経験し、在宅診療で患者を看取るやりがいに気づいた。

- 医療法人社団八心会上田医院【在宅診療科】佐藤拓道氏(46歳)
-
- ”リハビリを学ぶ場”として最適の環境でスキルアップ。自分らしい医療を実現した。

- 医療法人社団永生会永生病院【リハビリテーション科】野本達哉氏(44歳)
-
- 病理医から精神科医へ。“直接患者の役に立つ喜び”を転職によって手に入れた。

- 特定医療法人寿栄会 有馬高原病院【精神科】畑中薫氏(70歳)
-
- 子どもの進学を機に長野から茨城の病院へ。100点満点の転職を果たした

- 医療法人茨城愛心会 古河病院 整形外科部長【整形外科】中村信幸氏(53歳)
-
- 母の死から立ち直れたのは周囲の支えがあったから。今は私が患者とその家族を守る。

- 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 後期研修医【総合内科】栗本美緒氏(27歳)
-
- 専門を備えた総合内科医になりたい。理想の環境で腕を磨きつつ次世代の医師育成にも励む日々

- 医療法人社団保健会 谷津保健病院 診療部長(兼)内科部長【内科】須藤真児氏(49歳)
-
- 妻に恥じず子供に誇れる、自分が理想とする医療を後進とともに追求したいと願った

- 公益財団法人 東京都医療保険協会 練馬総合病院 循環器内科【循環器内科】伊藤鹿島氏(39歳)
-
- 日本初の北米式研修システムと都市部では希少なER式救急を通じ診断学と教育に強く関与したい

- 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急部【救急科】舩越拓氏(32歳)
-
- 通勤時間を惜しむほどの激務から自宅まで徒歩2分の病院に転職私生活を大切にできる環境へ

- 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院【化学療法科】中村将人氏(39歳)
-
- 大学の医局には入らず慢性期・急性期ともに学べるスーパー救急のある病院へ一直線

- 社会医療法人公徳会 佐藤病院【神経科】加藤舞子氏(31歳)
-
- 脳梗塞患者の回復していく姿を間近でずっと見守りたい。医師として切実な願いだった
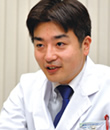
- 医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院【神経内科】藤田聡志氏(32歳)
-
- 多様化する医師のキャリア――製薬企業で創薬に医師としての経験を活かしたい

- ヤンセンファーマ株式会社 研究開発本部医療法人和会 渋谷コアクリニック(非常勤勤務)【精神科】高橋長秀氏(37歳)
-
- 大学病院から一般病院への転身。「本当に学べる場」との出会いが麻酔科医としてスキル向上に導く

- 医療法人社団順江会 江東病院【麻酔科】大見貴秀氏(32歳)
-
- 若く、キャリアが短いからこそ斡旋会社を利用。プロの力に助けられて、幸せな転職を叶える。

- 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 泌尿器科【泌尿器科】木田智氏(29歳)





