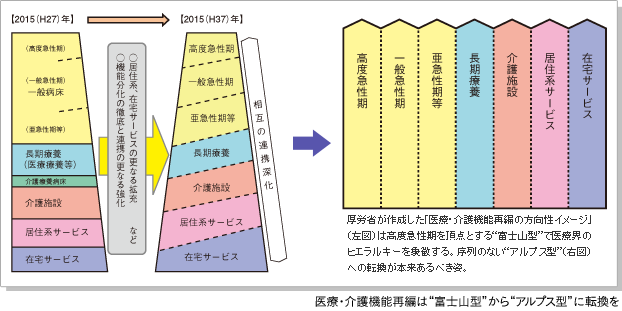-
戦後、高度経済成長期に作られ発展してきた日本の医療制度は、経済が安定成長期に入るとともに医療費抑制政策に転じた。結果として医療崩壊が引き起こされ、これから2025年問題に直面するにあたりその再生が大きな課題となっている。超高齢化、都市化、慢性疾患の増大などは医療界に大きなインパクトを与える。病院および医師はどう対応していくべきか。5人の論者が語る。
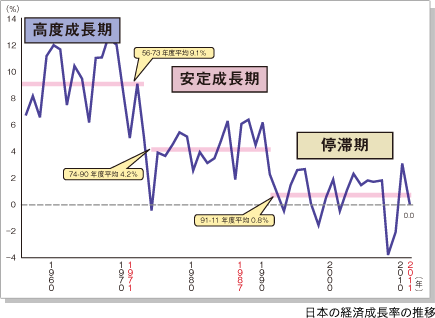
- 医療界大予測
2025年はこうなる!
- 1
患者の“多様性”に敏感な医師でなくては務まらない。
超高齢化・都市化に対応する「患者に寄り添う医師」が必要

- 西村 周三氏
- 国立社会保障・人口問題研究所所長、京都大学大学院名誉教授
- 京都大学経済学部卒業。同大学院を経て、京都大学助手、横浜国立大学助教授、京都大学助教授、同教授などを歴任。専門は医療経済学。同分野の日本における草分け的存在の1人で、医療経済学会の初代会長を務めた。共著書に『社会保障を日本一わかりやすく考える』(PHP研究所)、『社会保障と経済』(東京大学出版会)などがある。
-
図1は2060年までの日本の人口推計。総人口は48年には1億人を割り、60年には約9,000万人にまで減少する。一方で高齢化率は上昇を続け、25年には約30%、60年には40%になると推計される。
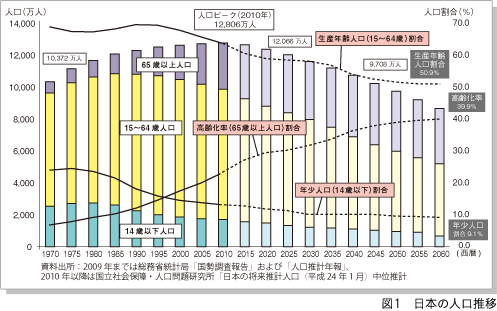
図1で示したように、国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」では、我が国の総人口はすでに減少期に入っている一方で、高齢者人口は増え続けています。いわゆる「団塊の世代」(1947~49年生まれ)が75歳以上となる2025年には高齢者が3657万人に達し、2042年にピークを迎えます。総人口が減少するなかで高齢者が増加するため高齢化率(65歳以上)は上昇し、2013年は25・1%で4人に1人となり、2035年には33・4%で3人に1人となります。
こうしたデータをもとに対策を講じる時、地域差に目を向けることの必要性は言うまでもありません。同時に比率と絶対数を分けて解釈することも非常に重要です。
地方の高齢化は止まり都市部では進み続ける
図2は、2025年までの都道府県別の人口と、75歳以上の人口の増加率を示しています。東京都はわずかに総人口が増えるものの、75歳以上の高齢者数が約130万人から約200万人に急増します。ほかにも愛知県、神奈川県、千葉県、埼玉県では総人口がほぼ横ばいで75歳以上の人口が急増しますから、国内の75歳以上の25%が都市部に集中する見込みです。大阪府や北海道では、総人口は減少するなかで75歳以上の人口が大幅に増え、高齢化率が高まります。一方で、鳥取県や島根県では、総人口が減りつつも75歳以上の人口増加も少ないので、今以上の高齢化は進まないと推計されます。
-
図2は都道府県別の75歳以上人口を示している。東京や神奈川など都市部では大幅に伸びる一方、鳥取や島根では伸び率が小さいことがわかる。
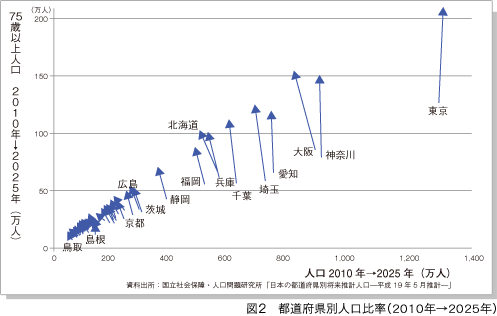
つまり、高齢者の割合は地方の方が多くても、絶対数は都市部のほうが圧倒的に多いわけです。都市部では75歳以上の患者を診る医師が大勢必要になります。しかし単に人数がいればいいのではなく、疾病構造の変化に対応できる医師が求められます。がんなどの急性期の疾患の好発年齢は60歳代で、75歳以上になると生活習慣病など慢性疾患の患者が増えます。手術に代表される急性期の治療より、複数疾病を抱えた患者の相談にのる医師が必要なのです。
生活習慣病の治療は、医療技術や医学的知識の提供に加え、患者に寄り添うヒューマンスキルが問われます。国内の糖尿病患者は約1700万人ですが、うち年に1回でも医療機関を受診する人は400万人にとどまります。理由はある意味簡単で、治療が非常に難しいからです。生活習慣病の治療は本人の努力にかかっている部分が大きく、“上から目線”で「食生活を改善しなさい」と言っても離脱してしまいます。
医師はもっと患者の多様性に想像力を働かせる必要があると思います。とくに大学病院の医師は「世の中は、医師が普段相手にしているような人間だけで成り立っているわけではない」ことに気づくべきです。医学的知識を伝えても生活習慣をコントロールできない人もいる。そうした人を治療できるのは、「一緒にがんばろうね」と寄り添える医師だと思います。
最近のメディアでは、生活保護バッシングなど、まじめな人と怠惰な人を二分する単純な見方がまん延していますね。しかし、人間が一定のルールからはみ出る時には非常に複雑な事情があるわけです。患者が医師の指導を守れないときも、その背景を個別に知る努力が必要であると私は考えます。
欧米ではNUDGE(ナッジ)といって、患者の背中を(穏やかに)押すようなアプローチがあり、医療現場でも推奨されています。たとえば肥満外来などで、積極的に患者に手をさしのべ、励ますなどして、患者の治療を継続し、効果を上げているそうです。かつて日本の医師は、もっと患者の生活習慣に介入していました。それが個人主義の普及でいつの間にか影を潜めましたが、今後は再び必要になるのではないでしょうか。患者の生活に密着した、ある意味で“おせっかい”な医師が増えてもいいと思うのです。
医師は、自分で進みたい道を選択できる数少ない職業で、たとえ失敗したとしても生活に困ることはありません。自由な利点をもっと自覚し、試行錯誤しながらノブリスオブリージュを果たして欲しいと思います。
2025年大予測・おすすめの本
『医療白書 2012年度版 ~地域包括ケア時代に迫られる、病院 “大再編”と地域医療 “大変革”』
西村周三編集委員代表監修(日本医療企画)
いわゆる2025年問題に関わる医療・介護の見通しを幅広く扱っている。超高齢社会に向けてのパラダイムシフトや、2025年に至る日本の医療・介護・社会の変革の行方などを、多彩な執筆陣が丁寧に論じる。
- 2
日常生活圏を基点とした「第三世代」の連携が始まる。
病院完結型から地域包括ケアを前提とした新しい医療IT連携へ

- 田中 博氏
- 東京医科歯科大学大学院 疾患生命科学研究部 システム情報生物学 教授
- 東京大学卒。同大学大学院医学系研究科修了、同大医学部講師、スウェーデン ウプサラ・リンシェーピング大学客員研究員、浜松医科大学助教授、米国マサチューセッツ工科大学客員研究員などを経て現職。日本医療情報学会前理事長兼学会長、情報計算化学生物学会(CBI学会)会長、オミックス医療研究会会長、地域医療福祉情報連携協議会会長。医学博士・工学博士。
-
戦後、高度経済成長を追うように発展・変化してきた日本の医療制度。経済が安定成長期に入ってほどなくして医療費抑制政策に転じ、小泉政権時に医療崩壊が社会問題化した。
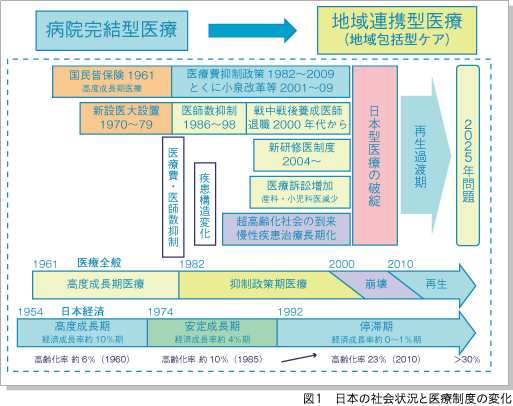
日本型医療は長い間「病院完結型医療」で、それぞれの病院が患者を治して退院させる、お互いに無関連な組織の集まりでした。しかし、それはそのころ我が国が若い人中心の国だったからできたことです。国民皆保険制度が始まった1961年は高度経済成長のまっただ中で、高齢化率は約6%。主な疾患は急性期疾患でした。治療が短期間で済むため、医療機関同士の連携がなくてもやり抜くことができました。
超高齢化社会を迎え、慢性期疾患中心となった現代は、複数の病院で患者を診る「地域連携型医療」が必須です。私は2025年に向けた再生過渡期だと考えています。そのためにITはより深く医療と関わるようになるでしょう。
-
田中氏は地域医療連携の歴史を第1世代~第3世代に分類する。現在は、地域包括ケアを前提とした第3世代にあたる。
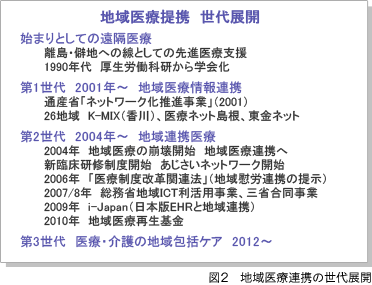
医療IT連携は、もともとは90年代に離島・僻地への遠隔医療支援として始まり、2000年代からは地域医療情報連携へと発展していった歴史があります。
当時の通産省は01年に「ネットワーク化推進事業」を立ち上げ、先進的な医療IT連携を行っている26地域に助成金を出しました。現在でも有名な千葉県立東金病院の「わかしお医療ネットワーク」などは、この時に登場した第一世代というべきケースです。地域全体で糖尿病を治療する循環型医療ネットワークとして注目されました。
ただ、第一世代はITの知識に長けた医師がいる地域で個別に発展してきました。また、各自がベンダーと契約してシステムを開発していたため、費用とマンパワーがネックとなり、他地域では同様の取り組みが難しい側面もありました。
それが各地に広がったのは00年代半ばでした。04年に新臨床研修制度が始まり地方の医師不足が深刻化した頃です。06年の「医療制度改革関連法」で地域医療連携の方向性が示され、07年には総務省の「地域ICT利活用事業」が始まりました。この時に登場したのが函館市の「道南MedIka」や長崎県の「あじさいネットワーク」などです(第二世代)。
日常生活圏内で多職種協同の連携
さて、2025年に向かうこれからは、第三世代となる新たな連携を進めていかなければなりません。キーワードは、「予防」と「地域包括ケア」。医療費削減には、ワクチンなどによる一次予防より、すでに疾病を抱えている患者の重症化予防のほうが数段、効率がいいことがわかっています。糖尿病患者を透析する状態にまで進めない、一度脳卒中をおこした患者に再発させない、といったことこそ、医療費削減のためにも、超高齢社会全体の質を高めるためにも、求められるようになるでしょう。そのために地域包括ケアを前提とした連携が必要になります。
これまでの医療連携の多くは二次医療圏単位でしたが、地域包括ケアを行うには、もっと小さい「日常生活圏」の連携が求められます。ちょうど小中学校の校区ほどに相当し、診療所、訪問介護・看護、役所の生活支援課、地域包括支援センターがまとまっているエリアです。この中で、医療と介護のシームレスな連携をするわけです。
すでにiPadを用いた電子連絡帳など、ITを用いた医療・介護連携を始めている例はいくつもあります。将来的には、地域のどの患者を誰が何時に診たか。往診や訪問診療はどのルートで回ると効率的かなどをマップで示すなど、さらに発展することでしょう。
現段階では多くの急性期病院は介護との連携に消極的ですが、国の事業として、急性期病院から慢性期治療や介護へのつながりの基盤となる「医療等ID(仮称)」も検討されています。もちろん医療・介護情報は機微な情報でセキュリティやプライバシー保護に十分な対策が必要ですが、連携した医療や包括的なケアの基盤となることは確かで、2013年中頃の法案提出を見込んでいます。急性期と慢性期がつながる仕組みができつつあるのです。今後は、病院勤務医も含め、医療界全体で地域包括ケアにかかわる時代になるでしょう。
- 3
急性期と慢性期の序列を廃し、慢性期医療の“ブランド化”を!
要求の多い「団塊の世代」に対応するには
医師の教育から意識転換が必要だ

- 梅村 聡氏
- 民主党参議院議員、厚生労働大臣政務官
- 大阪大学医学部卒業。同大学第二内科に入局し、同大学病院および箕面市立病院等に勤務。2007年、第21回参議院選挙で初当選。現在、厚生労働大臣政務官、民主党大阪府連幹事長代理、民主党参議院大阪選挙区第2総支部長。共著に『パンドラの箱を開けよう』(エピック)がある。
高度急性期が慢性期に勝っているわけではない
いわゆる団塊の世代が全員、後期高齢者になる2025年は、慢性期医療の充実が重要になることは間違いありません。医師のキャリアとして、慢性期医療への参入は、今後、大きな柱となることでしょう。
しかし、現段階では消極的な医師が多いのが現状です。中堅世代の医師の多くは「慢性期病院で働くのは第一線を退いてから」というイメージを抱いているのではないでしょうか。
そうした風潮を招いている一因が、厚生労働省が作成した「将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ」(上図・左)です。高度急性期医療を頂点とした“富士山型”の図で、官僚の頭の中にあるヒエラルキーをそのまま図示したがごとくです。まるで高度急性期医療がもっとも優れており、亜急性期や長期療養は2段も3段も劣っているように示されています。
慢性期医療の重要性を唱える一方、上下関係の意識が見え隠れする。厚生労働省がこのように医療・介護の方向性をとらえているうちは、慢性期医療の充実は難しいと言わざるを得ません。
私は、この図を90度横に倒した“アルプス型”の医療・介護モデルにすべきだと考えています(上図・右)。高度急性期も慢性期も、それぞれが同等の“山”で、そこに優劣は存在しない。慢性期医療への参入は決して富士山の“下山”ではなく、アルプスの隣の山に移るような横のつながりである連携体制が、2025年に向けて目指すべき道です。
臨床実習や卒後研修で慢性期医療を学ぶ体制を
慢性期医療を充実させるには、医師の教育においても、考え方の転換が必要になるでしょう。臨床実習や卒後研修で、慢性期医療を学べるカリキュラムを導入する必要があります。現行の研修制度では、基本的に急性期病院を中心とした内容になっていますから、高齢者の慢性疾患やリハビリテーションをあまり診たことのない研修医も珍しくありません。また、研修プログラムの目標は「○○ができるようになること」などと、急性期医療を前提とした技術取得にどうしても偏りがちです。
医療界が、こうした状態のままで2025年に突入することは非常に危険です。必ず、医師─患者間に、今以上の大きなミスマッチが生じます。
私は政治家ですから国民のニーズには敏感で、実際に直接話を聞く機会も多いのですが、医療に対する不満のなかでよくあるのは「自分の専門以外は診ない医師」です。なかでも、高度経済成長期を生き抜いてきた団塊の世代はそうした要求が多い。ストレートに表現するなら、団塊の世代は口うるさい高齢者になる可能性が極めて高い。私は、自分の親がまさに団塊世代なので、これは、確信を持って言えます(笑)。
このような患者と数多く接するうえで医師に大切になるのは、専門技術以前のヒューマンスキル、そして経験ではないでしょうか。
これは私見ですが、研修医の時期には、細かな技術を覚えるより、患者と誠実に向き合う経験を積むことが先決だと思います。若い医師のなかからは「慢性期は誰でもできる医療」という声も聞こえますが、実際は違います。高齢者の多くは複数の疾患を抱えており、最初の一手を間違えると大変なことになりかねない。高齢者の慢性期医療は、まさに、医師の経験がものをいう世界なのです。他の医師のバックアップが見込める急性期医療以上に、責任の重い局面があります。
厚労省は、超高齢化社会の備えとして在宅医療の拡充を強調しますが、在宅医療は連携先の病院があって初めて成り立つことを忘れてはなりません。2025年にはさらなる都市化が進んで高齢者が地方に住みにくくなるうえ、男性の未婚率が30%近くにものぼるというデータもあります。いずれ、病院勤務医も慢性期医療のスキルを身につけ、地域に出向く(出向かざるを得ない)時代になることでしょう。
2025年以降は団塊ジュニアに期待
先日、将来の認知症の患者数の予測数字が大きく上方修正される調査結果が発表されましたが、これから先、医療の現場で認知症の患者の診療はごくごく当たり前になります。今は急性期病院に認知症の患者が入院すると医療者側は身構えてしまいがちですが、早晩、特別なことではなくなるのです。
現場の対応力を高めるために、慢性期医療を“ブランド化”することは極めて重要になります。学会を盛り上げたり、研究しやすい環境を整備したりするほか、極端に言うと大学病院で慢性期を診るところがあってもいいのではないかと思っています。1つの病院がフラッグシップとなって慢性期医療の重要性を発信し、それを具現化するところが出てくれば、他の病院にも、また地方にも伝播して広がる可能性が期待できます。この10年ほどで病院経営者たちは慢性期医療に注目するようになりましたが、経営層の医師だけではなく、現場の医師たちも意識を転換する必要があります。もっと慢性期医療に注目してほしい。ここが、コアになっていくでしょう。
私が言うまでもなく、今の日本の医療は、決して安心できる状態ではありません。このままでいいわけがない。既存権益が複雑すぎて、大きな変革が難しい、という状態が続いており、なかなかチェンジが進みません。
しかし2025年には、団塊の世代の子ども世代である団塊ジュニアが50歳代に入ることに、私は期待を寄せています。私自身もそうですが、団塊ジュニアは人数が多いために競争にさらされて成長してきました。同時に、要求の多い親世代に鍛えられてもきました。この世代が意思決定者の年齢に達したときには、時代の流れに合った制度を作り、日本の医療を復活させる主戦力になることでしょう。
2025年大予測・おすすめの本
『最新型ウイルスでがんを滅ぼす』藤堂具紀著(文春新書)
著者は東京大学医科学研究所先端医療研究センター先端がん治療分野(脳腫瘍外科)教授。がん治療の新しいアプローチについて、具体的に知ることができる。そしてなによりベッドサイドで患者さんの悩みに接し、それに関わった医師の目からの研究が、今の日本の医学・医療にとって重要であることが再確認できる。多くの医師の方に触れて欲しい1冊である。
- 4
一部の専門医と救急医を除いて、医師は今までほどプレステージの高い職業ではなくなる。
医師のあり方が大きく変わる産業革命以来のパラダイムシフト

- 黒川 清氏
- 政策研究大学院大学教授、日本医療政策機構代表理事
- 東京大学医学部卒。同助手時代の1969年に渡米。ペンシルベニア大助手などを経て、79年からカリフォルニア大ロサンゼルス校(UCLA)教授。83年に帰国し、東京大学医学部助教授、同教授、東海大医学部長、日本学術会議会長、内閣特別顧問などを歴任。東京大学名誉教授。2011年12月より東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)委員長。『大学病院革命』(日経BP社)、『世界級キャリアのつくり方』(東洋経済新報社)など著書多数。
今、世界は産業革命以来の大きなパラダイムシフトを迎えています。2025年にやってくる超高齢化や都市化は、社会が求める医師像を大きく変えるでしょう。
交通網や交通手段の発達した都市部に人口が集中することによって、今後ますます生活習慣病が増大します。農作業などをしていた昔に比べて消費カロリーが大幅に下がっているのに、1日3回、同じように食べるわけですから当然です。先進国と途上国にも共通した悩みです。
食べ過ぎや運動不足で高血圧、糖尿病になった患者は、今後も医療の対象とし続けるべきでしょうか? 私は必ずしもそうではないと考えます。窮迫する医療財政や国民の健康維持の観点から考えると、生活習慣病は症状が進行する前の予防こそが重要だからです。医療より福祉や保健へとシフトさせる必要があります。
日本の医療制度は、およそ100年前の感染症が主たる疾病だった時代に作られました。感染症であれば医師が治療するのが妥当でしょうが、生活習慣病の予防は、医師以外の職種、すなわち看護師や保健師などでも可能です。いくつかの国では、以前からNP(ナース・プラクティショナー)が生活習慣病の診断や治療などを行っており、日本でも特定看護師のモデル事業が始まっています。こうした職種間のボーダレス化は、先進国において必然的な流れです。
患者のデマンドを察知し対応する能力が必要に
生活習慣病を医療から切り離すことになると、医師に対する社会の意識は大きく転換されます。一部の専門医と救急を除いて、一般的な臨床を行う医師は今までの社会ほどプレステージの高い職業ではなくなることでしょう。これまでのように病院で待っているだけではなく、患者のデマンドに応える努力が求められるようになります。 産業界にたとえて話しましょう。かつて日本のもの作りは「いいものさえ作れば売れる」時代が長く続きました。しかし現在は消費者が本当に必要とするか否かが勝敗を決めます。インドに本社を置くタタ・モーターズは20万円の超低価格車「ナノ」を発売して話題になりました。開発のきっかけは雨の中、子ども連れの家族が1台のバイクに乗っている姿をラタン・タタ会長が見かけたことといいます。自分たちがいいと思った商品を“PUSH”するのではなく、消費者のデマンド“PULL”に対応する。この発想の転換は医師にも同様に求められるでしょう。
歴史を振り返れば、医師のステータスが上がったのはほんの200~300年前からのことです。血液型のABOが分かったのは1900年。産婦人科医が、もともと市井の女性たちが経験に基づいて対応してきたものに代わりはじめたのもこのような背景です。
都市化に対応するためにはオープンシステム化が必要
一部の専門医や救急については、教育や医師の配置のあり方が変わっていくだろうと、私は予測しています。 まず外科医の必要人数は、これから手術の適応になる患者数と予測に基づいて算出されなくてはなりません。そのためには社会・医療関係統計を整備、公開することが先決ですが、100万人当たりの基幹病院と脳外科医などの数は予測できます。
その上で、迫り来る都市化、高齢社会に対応できるように医師や医療職を配置することです。東京都心の御茶ノ水周辺は、東大、順天堂大、東京医科歯科大、日大、日本医科大の付属病院などの大病院が密集しています。しかし、同じような機能を持つ病院が、これほど密集している必要はありません。いずれ集約化して、オープンシステムにすることが望ましいでしょう。地域の中心的な病院が北米型ERで救急を引き受け、ほかの病院や診療所の外科医や救急医、医療スタッフが交代で勤務する方法です。
経営母体が違うなどの諸問題があり、すでに取り組みを始めている某病院では労働組合からの反対に遭ったといいますが、医師は自分の周りだけでなく、大きくものを見なければなりません。単一の病院に閉じこもって働くという日本の常識を、根本的に変えるべきです。
実際、重要な局面ではすでにオープンシステム方式が生かされているではありませんか。2003年に行われた天皇陛下の前立腺手術は、場所は東京大学でしたが、執刀は東大と国立がんセンター(現・独立行政法人国立がん研究センター)泌尿器科の合同チームでした。病院はあくまでも“箱”にしか過ぎません。医師は能動的に、既存の組織の発想から抜け出て活動する時代になってきているのです。
世界の不平等を肌で感じて見えてくるもの
私は、高いスキルのある医師は、もっと世界で勝負して欲しいと願っています。天皇陛下の冠動脈バイパス手術の執刀医、順天堂大学の天野篤氏のように、世界最高水準の能力を持つ医師はいるのに、まだまだ海外での活躍が少なすぎると思います。
今後は、医師の教育システムそのものをグローバル化させていく必要があることでしょう。私は「休学のススメ」と言っているのですが、留学でも遊びでもいい。1年間休学してでも途上国も先進国も体験してくることは重要だと思います。世界の不平等を肌で感じ、日本がどのような立ち位置にあるかを知ることから、より大きな視点で医師として目指すべき方向が見えるでしょう。
英米の大学では学部学生にアフリカやインドなど途上国に行って現地での生活を体験するプログラムを推奨しています。日本でも東大では、学生が半年の間、休学して留学やインターンを体験する制度を導入し始めました。医療界のグローバル化は今後ますます進むでしょう。すでに40歳代以上の中堅医師は、若い世代が世界に羽ばたくための応援を惜しまず、日本の医師のすばらしいことを世界に広めて欲しいですね。
社会、あるいは世界にはどんなデマンドがあるか。また、自分はそれに対してどう応えられるか。その答えをしっかりと見定めながらキャリアを形成していく医師は、2025年になっても生き残ることでしょう。既存概念にとらわれず、新しい一歩を踏み出す勇気を持つ一人でも多くの医師の登場を期待しています。
2025年大予測・おすすめの本
『グローバルキャリアーユニークな自分のみつけ方』 石倉洋子著(東洋経済新報社)
これからの個人に求められる資質が書かれている書籍で是非、ドクターの皆さんにも読んでいただきたい1冊。
- 5
専門医としての「総合医」を育てる新制度が開始する。
専門医・総合医、勤務医・開業医の垣根を越え
医療界全体で医療の質を担保する時代へ

- 高久 史麿氏
- 日本医学会会長、地域医療振興協会会長
- 東京大学医学部卒。同大助手、自治医科大学教授、東京大学教授、同医学部長、国立国際医療センター総長、自治医科大学学長などを経て現職。東京大学名誉教授、国立国際医療センター名誉総長。自治医科大学名誉学長。
質の高い専門医を育てる新専門医制度を発足
2025年を迎えて最も医師に直接的な影響を与える問題は、疾病構造の変化です。複数の慢性疾患を持つ高齢者が患者の中心となり、総合診療のニーズが高まることでしょう。 私が座長を務める厚生労働省の「専門医の在り方に関する検討会」は、内科や外科など従来からある「基本領域専門医」(18領域)に、総合医・総合診療医を追加して19領域とする方向に意見がかたまりつつあります。
総合医と総合診療医のどちらの名称を採用するかについては現在、議論を重ねているところですが、私は名前にはさほどこだわりません。ただ、地域住民への健康教育や校医など幅広い役割を担ってもらうことを想定すると、総合医のほうが適切ではないかという意見があります。ここでは、便宜的に総合医としましょう。今後、総合医が1つの専門医として扱われることになる可能性が高いと思います。
総合医については、旧来の内科専門医とどう違うかと聞かれることがあります。確かに、両者の領域はオーバーラップする部分が多くありますが、総合医はより広い領域を対象にすることが検討されています。小児のコモンディジーズや産婦のフォローアップ。さらに、アメリカのファミリー・メディスンのように整形外科を含めてもよいと私は考えています。
主に総合医としての役割を担うのは地域の開業医になると想定されますが、2025年は高齢化に加え都市化の問題も差し迫っています。都市部では勤務医も在宅診療を担う可能性がありますから、総合医はあらゆる医師が関連するテーマであると言えるでしょう。
専門医の取得が診療科標榜の条件に
総合医が専門医になると同時に、専門医制度も大きく変わることになります。まず、総合医を含む基本領域専門医の取得には、5年間の研修を義務づけることになると思います。 また、現状の専門医制度は各学会が独自に認定していますが、新制度では、これから創設される第三者機関が客観的に評価する仕組みに移行するでしょう。各学会が作った研修プログラムの妥当性とアウトカムのチェックを行うための機関です。現在のところ、第三者機関は(社)日本専門医制評価・認定機構を母体として組織される見込みですが、医療者だけでなく、メディア関係者や患者の代表など医療界の外部の人を含めた方が良いと私は思います。
なお、新専門医制度が開始した以後は、しばらく時間はかかりますが、いずれ自由標榜制は廃止される方向にいくと思います。病院でも診療所でも、専門医を標榜するには基本領域専門医のいずれかを取得することが条件になる時代がくるでしょう。これは、患者の信頼を高めるための措置でもあります。地方の医師会長の先生から聞いた話ですが、最近は若手医師が開業し、5つも6つも診療科を標榜して、医療の信頼を失墜させている例があるそうです。こういった事態を減らすことは、医療界にとって重要です。アメリカではレジデントとして研修を受けなければ“看板”を出すことができません。
厚生労働省は13年に第三者機関を創設し、15年に新専門医制度をスタートさせようとしています。まずは若手医師の後期研修の代わりとして始動する予定で、既に専門医を取得した医師の移行措置については現在議論を進めているところです。外科をリタイアして内科に転科する医師も研修を受けるかどうかなど、慎重に対応策を決めなくてはなりません。
医師の地域偏在解消は医療界のオートノミーで
新専門医制度の導入や自由標榜制の廃止には、診療科ごとの医師数偏在を是正する効果も期待されています。しかし地域偏在については、別途、医療提供体制自体の見直しが必要だと私は考えています。地方に住む高齢者が増える2025年に向けて、地域偏在の解消は非常に大きな課題です。一部では国が医師の強制配置を行うべきだとする声もありますが、「他」から言われてやるのではなく、私は医師の配置は医師が自分たち自身で、オートノミーを発揮して取り組むべき問題だと思います。
そこで参考になるのがドイツの例です。ドイツでは、医師会や大学、第三次医療機関などが自律的に医師を配置し、地域や診療科の偏在を防いでいます。医師が医師会へ加入することを法律で義務づけられているドイツだからできる方法でもありますが、日本も同様の法律を整備してもよいのではないでしょうか。すでに弁護士は弁護士会に強制加入となっていますが、医療界でもできないことはないはずです。日本医師会には、新専門医制度の第三者機関を支えるようにしていただきたいと考えています。
従来型の医療提供体制から大きな転換を迫られる2025年は、専門医・総合医、あるいは勤務医・開業医という垣根を超えて、医療界全体で医療の質を担保し、患者および社会の、医療に対する信頼を高めていくことが重要です。
2025年大予測・おすすめの本
『寝たきり老人ゼロ作戦』 山口昇著(ぎようせい社)
高齢者が寝たきりにならないために、著者の勤務する病院で行われた具体的な方策を紹介。原則的には国が作った「寝たきりゼロへの10か条」をベースに、患者本人向けと家族向けの10か条を作っている。高齢者医療の根本を考える際の参考となる一冊。
常時10,000件以上の医師求人。専任のキャリアアドバイザーが、ご希望に合う転職をサポートします。
転職・アルバイトのご相談はこちら医師のキャリア支援情報誌『リクルートドクターズキャリア』掲載の特集一覧
-
- 医師のキャリアプランを考える
- 医師は生涯現役で活躍できる一方で長期的なビジョンをもって主体的にキャリアを築くのは意外と難しいが、成り行き任せでは絶好の機会を逃すことにもなりかねない。キャリアのステージごとに選択のポイントを探る。
-
- 増える「地域包括ケア病棟」デビュー
- 急性期に携わっている医師も、そう遠くない将来、“地域包括ケア医”になるかもしれない。地域包括ケア病棟の現状や課題と、そこで求められる医師像を紹介する。
-
- チーム医療と医師のキャリア
- 医学の進歩、高齢化の進行などによりチーム医療の充実が必要とされ、診療報酬に加点がつくなど国を挙げて推進する意向も見てとれる。チーム医療に詳しい医師に、チーム医療の本質と現状、求められるスキルを聞いた。
-
- これからの精神科病院
- 精神科医療のニーズは高まり続けている。厚生労働省調べでは患者数は約320万人で、がん患者の約2倍にのぼるが、国は精神科病床の削減を強化している。最前線の病院に今後の精神科医療を取材した。
-
- 女性医師のキャリアと働き方
- 女性医師が着実に増える一方、結婚や出産・育児でキャリアの中断を余儀なくされる場合も多い。女性医師の置かれた現状を知り、働き続ける工夫やヒントを探るためにケーススタディを見てみよう。
-
- 医師が選ぶ 臨床以外のフィールド
- 医師の働き方や活躍の場は多様化しつつある。臨床ではない「起業家」、「法医学者」、「医系技官」、「企業人」の転機のきっかけ、仕事、適性ややりがいを聞いた。
-
- 医師のキャリアプランの考え方
- キャリア年数や年代、診療科、働き方の希望によってベストな選択は異なる。将来を見据えて早めにプランを組むことで、自分らしいキャリアパスを手に入れよう。
-
- 産業医の現場事情
- 企業内で従業員の健康管理に携わる産業医は、興味を持つ医師も多い人気の職業と言われる。具体的な業務内容、専属と嘱託の違い、必要な要件は何かなど、業界の動向と現役産業医の事例を紹介する。
-
- 医師の転職マニュアル
- キャリアアップ、ゆとりのある働き方など、転職の理由はさまざま。満足度の高い転職を実現させるための基礎知識とポイントを網羅した「転職マニュアル」の保存版。
-
- 生涯現役で働くためのキャリアプラン
- 勤務医は定年後を見越してキャリアプランを立てる必要がある。シニアドクターの転職事情やノウハウと事例を紹介する。
-
- 医師のキャリア 誌上相談
- 「方向性が正しいか不安」、「キャリアデザインが描けない」など転職に関する悩みはさまざま。転職を支援するキャリアアドバイザーが解決した事例から成功のヒントを探る。