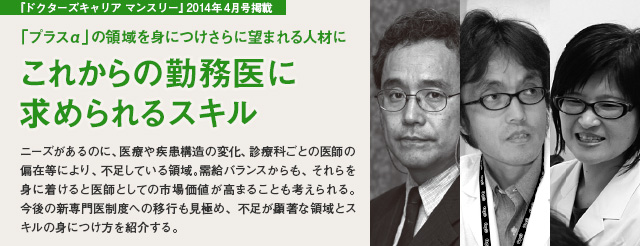疾病構造の変化に合った臨床医が求められている
生活の変化と高齢化で日本人の疾病構造は大きく様変わりした。いまやがんや糖尿病、脂質異常症や高血圧性疾患を避けて通ることは難しい(表1)。加えて、高度医療による救命率向上は再発リスクや後遺症を抱える患者を増やし、超高齢社会の到来は複数の慢性疾患を併せ持つ患者を増やし続けている。
この現状に対峙するには、旧来の臓器別診療や細分化された専門性では限界があるとみる現場の声は少なくない。同時に、患者ニーズの多様化や治療法の変遷、医療に期待される役割に対応すべく、医師にも新たな専門性やスキル、診療姿勢が求められている。
なかでも、複数の合併症を抱えて診療科の狭間で行き場を失いがちな患者を、包括的に診療するスキルをもつ総合診療医は、高齢化がピークに向かう昨今、引く手あまただ。
同様にがん治療においては、副作用対策も含む薬物療法を自己流ではなく「適切に」行える腫瘍内科医、がんに伴うさまざまな苦痛症状を和らげる緩和ケア医のスキルが、診療現場では強く求められている。
表1 主な傷病別総患者数
(単位:千人)
| 主な傷病 | 総数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成8年 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |
| 結核 | 91 | 71 | 47 | 39 | 27 | 26 |
| ウイルス肝炎 | 405 | 380 | 412 | 410 | 313 | 206 |
| 悪性新生物 | 1,363 | 1,270 | 1,280 | 1,423 | 1,518 | 1,526 |
| 糖尿病 | 2,175 | 2,115 | 2,284 | 2,469 | 2,371 | 2,700 |
| 高脂血症 | 964 | 1,140 | 1,391 | 1,530 | 1,433 | 1,886 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 91 | 121 | 138 | 145 | 143 | 146 |
| アルツハイマー病 | 20 | 29 | 89 | 176 | 240 | 366 |
| 高血圧性疾患 | 7,492 | 7,186 | 6,985 | 7,809 | 7,967 | 9,067 |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 2,039 | 1,845 | 1,667 | 1,658 | 1,542 | 1,612 |
| 脳血管疾患 | 1,729 | 1,474 | 1,374 | 1,365 | 1,339 | 1,235 |
| 食道,胃及び十二指腸の疾患 | 2,338 | 1,923 | 1,630 | 1,559 | 1,345 | 1,246 |
| 肝疾患 | 606 | 459 | 350 | 312 | 247 | 276 |
| 骨折 | 404 | 409 | 406 | 455 | 510 | 542 |
注:平成23年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値
厚生労働省「平成23年患者調査」より一部抜粋
専門性を生かしながら診療のレベルアップを図る
しかしながら、これらを専門とする医師の数は圧倒的に不足している(表2)。
卒後10~15年経ち、専門医として独り立ちした医師が、現場で直面する課題にどう向き合い、次なるステップをどう踏み出すか。これまでの経験と専門性を生かしながら、より豊かで質の高い臨床を目指したい人に向けて、「これからの勤務医に求められるスキル」として、いくつかの領域を紹介したい。今回は、総合診療、腫瘍内科、緩和ケアの3領域にスポットを当てる。
ある病院の経営幹部は「必ずしも専門医資格がなくても構いません。その領域を“診る力”のある先生は、患者さんにも喜ばれますし、病院にとっても本当にありがたい存在です」と語る。 医師転職会社のキャリアアドバイザーも「たとえば普段がん治療に携わる方で、緩和や腫瘍内科を学ばれたご経験があれば、転職のときにアピールポイントになります」と話す。転科ほど大げさな「キャリアチェンジ」ではなく、現在の専門領域の“周辺”に、ヒントを探したい。
表2 関連領域専門医数
| 認定学会名 | 専門医名称 | 専門医数 | 調査時期 |
|---|---|---|---|
| 日本内科学会 | 総合内科専門医 | 15,497名 | 2014年1月現在 |
| 日本プライマリ・ ケア連合学会 | 家庭医療専門医 | 385名 | 2013年8月現在 |
| 日本リハビリテーション医学会 | リハビリテーション科専門医 | 1,927名 | 2014年2月末現在 |
| 日本臨床腫瘍学会 | がん薬物療法専門医 | 867名 | 2013年3月2日現在 |
| 日本緩和医療学会 | 緩和医療専門医 | 58名 | 2013年4月現在 |
これからの勤務医に求められるスキル『総合診療科』
守備範囲を限らない診断のプロに
2017年度に始まる新専門医制度では、総合診療が新たに基本領域(*1)に加わる。名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学講座教授の伴信太郎氏の言葉を借りれば、総合診療医とは「領域を細分化する専門性ではなく、総合する専門性を有する医師」のことだ。
総合診療医は、あらゆる健康上の問題や疾病に対し、身体・精神の別なく総合的・継続的に、かつその人を取り巻く背景も含めて全人的に対応することが求められる。そのため幅広い知識と高い診断能力が要求される。
加えて、どの病院にも1割程度存在する“所属科不明の患者”の受け皿となり、現代医学では診断のつかない病態にもじっくり向き合っていくことも、総合診療医の務めであり、やりがいでもあると伴氏は考える。
スキル習得は実地研修あるのみ。目標は「患者を断らない医師」
こうした臨床能力は経験によってのみ培われるが、現時点で既卒者を対象とした公式な研修プログラムはない。希望者がこれぞと思う診療所や病院の総合診療科の門をたたき、一定期間研修するのが通例だ。
伴氏のもとにもこれまで多くの医師が研修に訪れ、外来でトレーニングを積み、毎日カルテのレビューを行うことで総合診療を学んできた。研修期間は週1~2回の外来研修で最短で1年、長い人で4~5年だという。「おおむねどのような患者が来ても診療できる自信がつくまでが目安」(伴氏)だ。ただし、放射線科や外科系の医師に比べ、内科系の医師の研修期間は相対的に短くて済むようだ。
すでに専門性を持った医師が改めて総合診療を学ぶことにはどんな利点があるのだろうか。
「まず、専門外のことを経験すると専門領域における発想が豊かになって、柔軟性も身につく。そして何より大きな変化は、さまざまな疾患の診断から治療まで一人で担えるようになることです」(伴氏)。
昨今、救急当番もできないような専門医も増えていると聞くが、総合診療のスキルが身につけば、少なくとも「専門外」を理由に診察を断るようなことはなくなる。もちろん、専門的な対応が必要な場合には、しかるべき専門家に紹介することになるが、そのようなケースは実際には救急患者の10~15%程度だという。
大学から地域まで需要はあらゆる場に
総合診療医のニーズは大学病院から地域のクリニックの家庭医にまで連続的に拡がっている。高齢化が進行すると、複数の慢性疾患を併せ持つ患者も増えてくるが、コモンディジーズのために5つも6つも診療科をはしごできるのは元気なうち。まとめて一人の医師に診てもらえるなら、患者からすると利便性も安心感も格段に増す。
また、都市部以外の地域では各領域の専門家を揃えられる施設は少ない。守備範囲の広い医師は何をおいてもありがたい存在だ。院内たらいまわしが減れば、地域における病院の評価も上がる。最近は在宅部門を設ける病院も増え、総合診療のスキルをもつ医師は、活躍の場にはこと欠かない。歓迎する施設は数多い。
また、活躍の場を地域全体を活動範囲と考えるなら、医療だけではなく健診や予防接種などの保健活動、在宅にも手を広げたいなら福祉や介護・生活支援にも無関心ではいられない。同じ総合診療でも、どこで活躍するかによって、習得すべき知識やスキル、構築するネットワークは違ってくる。
専門性が細分化してジェネラルな臨床能力が得にくい反面、近年、情報へのアクセスが容易になり、総合診療医に必要不可欠なEBMの実践がしやすくなっている。
「今後ますます、総合診療医が活躍できる時代になる」(伴氏)。
*1 日本専門医制評価・認定機構は平成25年8月現在、小児科や外科、整形外科など18の基本領域専門医制度と29のサブスペシャリティ領域専門医制度を承認している。

- 伴 信太郎氏
- 総合診療科
名古屋大学大学院医学系研究科 総合診療医学講座 教授 - 1979年京都府立医科大卒、同大小児科、米国クレイトン大家庭医学科レジデント、国立長崎中央病院(現長崎医療センター)研修指導医、川崎医大総合臨床医学教室准教授等を経て、98年10月より現職。
これからの勤務医に求められるスキル『腫瘍内科』
抗がん剤の副作用対策は必要不可欠の専門スキル
「抗がん剤治療において最も大事なことは、起こり得る副作用を熟知し、きちんと対策が行えること」と明言するのは、日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之氏だ。たとえば白血球減少は抗がん剤の副作用としてほぼ必発であり、白血球減少時の感染は抗がん剤の副作用死の原因のトップだ。抗がん剤を使うからには、感染症対策はもれなく心得ておかねばならない。
ところが、白血球数が下がるとすぐに抗がん剤の量を減らす、一週間に何度も採血する、白血球を増やすG-CSFを過剰に使う、生ものを食べることを禁止する、入院させる、マスクをさせる…などなど、対応には誤解も多い。「白血球減少時には特定の抗生物質を用いる」とガイドライン(*1)にも明記されているが、実際には、不適切な抗生物質の使用による死亡例も少なくないという。
下痢も侮れない。幅広い癌腫に用いられるイリノテカンが引き起こす重篤な下痢は、脱水症状で死に至ることもある。遺伝子検査で高リスク者の抽出が可能になった現在でも時折起こる。「唯一、助ける手立ては大量ロペラミド療法(*2)」(勝俣氏)。海外では標準的なこの治療もわが国では知らない人の方が多い。仮に知っていても、通常の6倍量のロペラミドを実際に用いるのには勇気が要る。副作用対策を含む腫瘍内科のスキルは、理論だけでなく、手本となる指導者についてベッドサイドで学ぶ必要があるのだ。
腫瘍内科に必要なのは、知識と経験、コミュニケーションスキル。きちんとした研修施設であれば、3ヵ月である程度抗がん剤治療のマネジメントが体得できる。
国立がん研究センター勤務時代には地方の外科医の1ヵ月研修も受け入れてきた。「誤解を恐れず極論すれば、1日2日見学するだけでもいい。自分たちがやっていなかったアプローチを目の当たりにして、目から鱗が落ちるだけでも、必ず得るものがある」と勝俣氏は考える。
この領域では最新のエビデンスについていくことが必須であるが、それを障壁と感じる医師も少なくない。勝俣氏は、「EBMの基本は、いかに早く最新最良のエビデンスを簡便に見つけるか。ノウハウさえ掴めば誰にでもできる。教えます」と話す。
「見捨てない」「引き際を知る」そのために必要なスキルは?
腫瘍内科の真のスキルはディシジョンメーキング(治療方針の決定)に集約されるが、同時に、それをきちんと伝えるためのコミュニケーション能力も問われる。
がん医療の目標は『治癒』とは限らない。医師が患者から逃げずに、最後まで共に考え支える。
「もう治療はありません」と言い放つのは言語道断だが、延命効果が望めないことをわかっていながら、亡くなる直前まで抗がん剤治療を続けることも、コミュニケーション不全が生む悲劇だと勝俣氏は指摘する。
基本は内科だが、がん診療にあたる外科医への期待も大
日本臨床腫瘍学会の認定するがん薬物療法専門医の数は現時点で900名に満たない。これでは、地域偏在どころかがん診療連携拠点病院への配置さえおぼつかない。一方、患者・家族、拠点病院以外の施設からも腫瘍内科のスキルは強く求められており、専門医不足とニーズとの隔たりを埋める医師の育成は急務だ。
勝俣氏は「その名の通り、内科の素養があることが基本だが、日々がん薬物療法の難しさ、診療の不全感に悩む外科医もぜひ一歩踏み込んで、確かなスキルを身につけて欲しい」と願う。そうすることで、治療効果も患者満足度も、人材としての価値も確実に上がるはずだ。
*1 発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン 日本臨床腫瘍学会 (編集) 南江堂2012
*2 本邦では用法・用量が適応外。

- 勝俣 範之氏
- 腫瘍内科
日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 教授 - 1988年富山医科薬科大学医学部医学科卒、茅ヶ崎徳洲会総合病院内科レジデント、国立がん研究センター中央病院・薬物療法部薬物療法室医長、乳腺科・腫瘍内科外来医長等を経て、2011年10月より現職。がん薬物療法専門医。
これからの勤務医に求められるスキル『緩和ケア』
がん治療医が担う緩和ケアの底上げが重要
2006年のがん対策基本法成立により、全てのがん診療連携拠点病院に緩和ケアチームの設置が義務付けられた。しかし実際には内科や外科、麻酔科の医師が兼任しており、緩和ケアは十分患者に届いているとはいい難かった。そこで本年1月の拠点病院指定要件改訂で、緩和ケアは「がんの診断時から提供され」「身体的・精神心理的・社会的苦痛等のスクリーニングを診断後早期に行う」ことが新たに盛り込まれた。
埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長の余宮きのみ氏はこれを「緩和ケアの質を上げる画期的な改訂」と高く評価する。
しかし、余宮氏の施設のように緩和ケア科6名、精神腫瘍科2名の医師のいる緩和ケア科ですら、チーム運営と病棟管理ですでに手一杯。大半の施設の深刻な人手不足に対応するには、すべてに緩和ケア医が対応するのではなく、がん治療医自身、あるいはチームとの連携で対処できる範囲の充実も重要だ。
日本緩和医療学会も、がん診療を行う医師すべての緩和ケアスキルの底上げと、緩和医療専門医養成の二段構えで緩和ケアの普及・推進に取り組む構えだ。
症状×病態の組み合わせは無限。症例数で研修先を選ぶ
がん治療医として最低限の緩和ケアを身につけるには、通常1~3カ月、緩和ケア医に転向する場合には最短で2年の研修期間が必要だ。余宮氏の施設にも全国から研修医が集まる。
日本緩和医療学会の2012年調査報告によると、登録された全国481の緩和ケアチームのうち、チームへの依頼が年間3~4百件を超える施設は、余宮氏のチームを含めてわずか4%だ。
「症状と病態の組み合わせは無数にある。症例の多い施設なら3カ月ほどである程度のパターンが経験できる」(余宮氏)。
緩和ケアのアウトカムは患者の満足度。技術が足りないと医者も患者も苦しい。だからこそ、緩和ケア医は豊富な選択肢を持たなければならないという。
1日のみの研修希望者も多いが、それでも得るものは大きい。
「患者に対する態度が(自院のそれと)全く違う」「切り口や視点の違いに衝撃を受けた」「本物の緩和ケアに触れ医療観が変わった」などの声が寄せられる。
視点の違いに気づくと薬の選択肢が変わる。「緩和ケア医の知識の豊富さを知り、『悩んだときに迷わず相談しよう』と思ってもらえるだけでも、緩和ケア全体の質は向上する」(余宮氏)。
第四の治療として注目度を増す緩和ケア
「早期から緩和ケアを受けている患者の生存期間が、そうでない患者に比べて延長している」ことを示す介入試験の結果が、2010年NEJMに掲載された(*1)。緩和ケアの直接効果を示すものではないが、早期から緩和ケアを受けることでQOLが保たれ、抑うつや身体症状が減り、無駄な抗がん剤治療も減る。これらが間接的に延命に結び付いたものと考えられている。
次々と新たな抗腫瘍薬が登場し患者の選択肢は増えたが、苦痛を緩和できず全身状態(PS)が悪ければ治療薬の恩恵は受けられない。いまや緩和ケアは「手術療法」「化学療法」「放射線療法」に並ぶ第四の治療といえる。苦痛で死にたいと絶叫する患者を30分後には笑顔にできる緩和ケアのスキルは、苦しむ患者を迅速に癒す、医師の原点でもある。
痛ければ鎮痛薬、吐き気があれば制吐薬、便が出なければ下剤を処方すればよいとの誤解も多いが、原因を無視した処置はかえって患者を苦しめる。重ね重ね、確かなスキルが求められる領域である。
緩和ケアの最新治療に精通し、専任以上(*2)で従事できる医師は、QOLを重視する患者、拠点病院をはじめとするがん治療施設から強く求められている。
*1 *1Jennifer S. Temel et al. Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer (NEJM 2010; 363:733-42)
*2 「専任」は50%以上、「専従」は80%以上その業務に携わることを指す
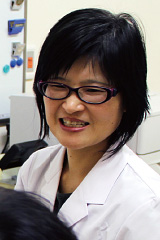
- 余宮 きのみ氏
- 緩和ケア
埼玉県立がんセンター 緩和ケア科科長 - 1991年日本医科大卒、内科、神経内科を経て同大リハビリテーション科に入局。2000年より埼玉県立がんセンター緩和ケア科、09年より現職。日本緩和医療学会専門医・理事、同学会緩和医療ガイドライン作成委員など。
常時10,000件以上の医師求人。専任のキャリアアドバイザーが、ご希望に合う転職をサポートします。
転職・アルバイトのご相談はこちら医師のキャリア支援情報誌『リクルートドクターズキャリア』掲載の特集一覧
-
- 医師のキャリアプランを考える
- 医師は生涯現役で活躍できる一方で長期的なビジョンをもって主体的にキャリアを築くのは意外と難しいが、成り行き任せでは絶好の機会を逃すことにもなりかねない。キャリアのステージごとに選択のポイントを探る。
-
- 増える「地域包括ケア病棟」デビュー
- 急性期に携わっている医師も、そう遠くない将来、“地域包括ケア医”になるかもしれない。地域包括ケア病棟の現状や課題と、そこで求められる医師像を紹介する。
-
- チーム医療と医師のキャリア
- 医学の進歩、高齢化の進行などによりチーム医療の充実が必要とされ、診療報酬に加点がつくなど国を挙げて推進する意向も見てとれる。チーム医療に詳しい医師に、チーム医療の本質と現状、求められるスキルを聞いた。
-
- これからの精神科病院
- 精神科医療のニーズは高まり続けている。厚生労働省調べでは患者数は約320万人で、がん患者の約2倍にのぼるが、国は精神科病床の削減を強化している。最前線の病院に今後の精神科医療を取材した。
-
- 女性医師のキャリアと働き方
- 女性医師が着実に増える一方、結婚や出産・育児でキャリアの中断を余儀なくされる場合も多い。女性医師の置かれた現状を知り、働き続ける工夫やヒントを探るためにケーススタディを見てみよう。
-
- 医師が選ぶ 臨床以外のフィールド
- 医師の働き方や活躍の場は多様化しつつある。臨床ではない「起業家」、「法医学者」、「医系技官」、「企業人」の転機のきっかけ、仕事、適性ややりがいを聞いた。
-
- 医師のキャリアプランの考え方
- キャリア年数や年代、診療科、働き方の希望によってベストな選択は異なる。将来を見据えて早めにプランを組むことで、自分らしいキャリアパスを手に入れよう。
-
- 産業医の現場事情
- 企業内で従業員の健康管理に携わる産業医は、興味を持つ医師も多い人気の職業と言われる。具体的な業務内容、専属と嘱託の違い、必要な要件は何かなど、業界の動向と現役産業医の事例を紹介する。
-
- 医師の転職マニュアル
- キャリアアップ、ゆとりのある働き方など、転職の理由はさまざま。満足度の高い転職を実現させるための基礎知識とポイントを網羅した「転職マニュアル」の保存版。
-
- 生涯現役で働くためのキャリアプラン
- 勤務医は定年後を見越してキャリアプランを立てる必要がある。シニアドクターの転職事情やノウハウと事例を紹介する。
-
- 医師のキャリア 誌上相談
- 「方向性が正しいか不安」、「キャリアデザインが描けない」など転職に関する悩みはさまざま。転職を支援するキャリアアドバイザーが解決した事例から成功のヒントを探る。