岐阜大学医学部附属病院 整形外科 教授に聞く 教育方針と未来
全整形外科疾患を県内で診られるように
さらには研究成果を世界へ発信
岐阜大学医学部附属病院整形外科学講座では、「大学らしい教室」を目指して、すべての整形外科疾患の診療体制を確立。基礎研究、臨床研究、教育でも様々な改革を行ってきた秋山治彦教授に、その方針と今後について伺います。
基礎研究や医師主導治験、
先進的整形外科治療で
医療の発展に貢献
-
岐阜大学医学部附属病院
整形外科 教授 - 秋山 治彦 先生
- 1988年
- 京都大学医学部卒業
- 1989年
- 松江赤十字病院整形外科
- 1991年
- 神戸市立中央市民病院整形外科専攻医
- 1998年
- 京都大学大学院医学研究科修了
- 1999年
- テキサス大学MDアンダーソン癌センター
- 2004年
- 京都大学医学部整形外科助手
- 2007年
- 京都大学産官学連携准教授
- 2012年
- 京都大学医学部整形外科学准教授
- 2013年
- 岐阜大学医学部整形外科教授
岐阜大学医学部整形外科の方針について教えてください
2013年に私が岐阜大学に着任したときは、教室のことだけでなく、岐阜県や岐阜市のことをほとんど知らない状態でした。教授に就任することが決まって以降、様々な情報を集めるなかで、医局が目指す方向性として思い描いたのは、「大学らしい教室にする」ということでした。「大学らしさ」とは、医局だけではなく関連病院の協力のもと、岐阜県内で専門性の高い整形外科診療を実践していくこと、さらに基礎研究と臨床研究や教育にも力を入れていくことです。また、岐阜大学の整形外科学講座での取り組みを広く発信していくことも重要だと考えました。
私が着任した当時、臨床に関しては国内で標準的に行われている手術手技が網羅できていない状況でした。医師の数が少なく、岐阜県全体で考えても診療体制を整えることの難しさはありましたし、岐阜県はがん専門病院がないため、悪性腫瘍の患者さんもすべて大学で診られる体制を整えなければなりません。すべての整形外科疾患を岐阜大学で診られるようにすることを目指して、まずはそれまでなかった手を専門とするグループを作り、さらに専門性を高めた診療グループの構築を行いました。
そのうえで、若い先生方にはカンファレンスを通じて「全国または世界レベルの治療ができることを目指す」という話をし、そのためのトレーニングを各グループで行ってきました。現在は、脊椎、股関節、膝・足関節、肩・肘、手、リウマチ、悪性腫瘍、リハビリテーションの8グループでそれぞれ専門性を追求してレベルの高い診療を実践しており、外傷に関しては高次救命治療センターで整形外科医が治療を行う体制を整えています。また、小児整形外科に関しては、関連病院の小児専門病院で診ています。
本大学の特徴として、リハビリテーション科が整形外科のなかにあることが挙げられます。リハビリテーションには運動器だけでなく、心臓、がん領域などもありますが、整形外科に限っていえば、整形外科で扱う運動器の疾患と運動器のリハビリテーションが密接に連携して細かな指示のもと、個々の患者さんによりよいリハビリテーションを提供できる点が強みだと思います。
研究ではどのようなことに力を入れていますか?
各自がテーマを持って臨床研究に取り組み、それを学会で発表し、英語論文として世界に発信することが必要だと考えています。もうひとつ、大学の使命ともいえるのが、基礎研究への取り組みです。以前は、大学院生は外部の研究室で基礎研究を行ってきましたが、私が就任して以降、岐阜大学整形外科学講座の実験室で行うようにし、私や他のスタッフが研究指導にあたっています。整形外科医の視点から、整形外科医が知りたいことや自身がやりたい研究を行うには、教室内にその環境を整えることが大事だと考えました。私をはじめ、長年基礎研究を続けているスタッフもいますので、そのテーマを後輩に受け継ぎ、伝えていくことも教育のひとつだと思っています。
研究テーマは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)などの研究費が得られる臨床に沿ったものを意識して選定していくことも、医療の発展を担う大学の役割のひとつです。また、岐阜大学の取り組みを広めるためにも、臨床試験は積極的に進めていきたいと考えています。現在も岐阜大学が研究主体となって、AMEDの支援のもと東京大学、京都大学、大阪大学とともに、指定難病である特発性大腿骨骨頭壊死症の医師主導治験に取り組んでいます。
こうした研究への取り組みは、全国、あるいは世界的に認められるものであり、医療の発展に寄与すると同時に、岐阜大学のアピールにもつながります。実際に私が教授に就任することが決まったとき、岐阜大学整形外科学講座ではどのようなことに力を入れているのか、どんな特徴があるのかなど、まったく情報は持っていませんでした。それを調べるにあたっても教室のホームページはほとんど更新されておらず、全国の医師や地域の患者さんに教室のことを知っていただく場もなかったのです。岐阜大学の整形外科がどんなことに取り組んでいるのかを広く知っていただくことも大切ですので、現在は年1回、教室のホームページを更新し、教室の行事や学会での様子などはフェイスブックを利用して紹介しています。多くの方にみていただくことで、岐阜大学整形外科学講座に関心を持ってもらうきっかけになればと思っています。
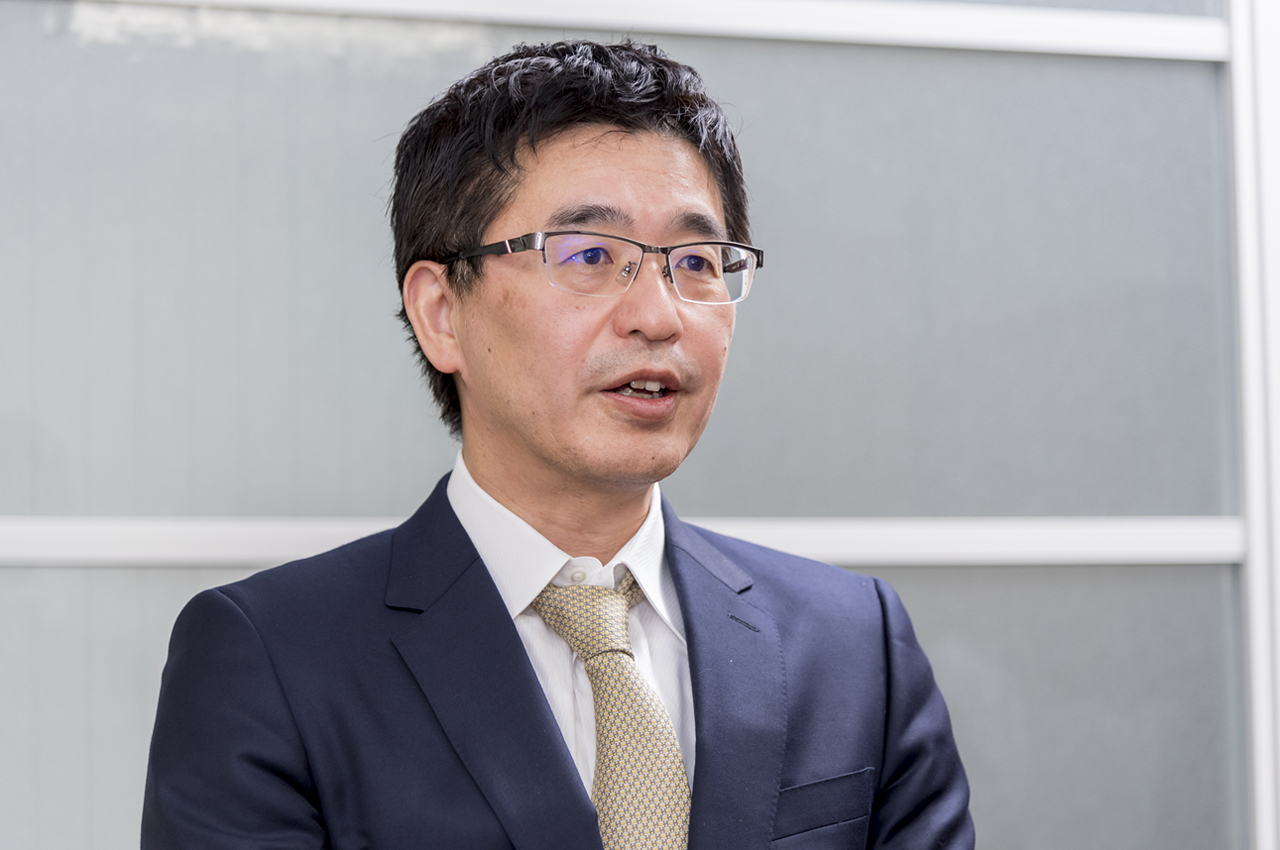
後期研修の特徴やその後のキャリアプランについて教えてください
整形外科の後期研修は、新専門医制度で45単位が必要となり、若い先生方には基本的な整形外科治療から最新の治療まで幅広く、そして多くの症例を経験してもらうことを重視しています。その後は大学院に進む、あるいは臨床でサブスペシャリティの領域の経験を積むなど、それぞれがキャリアメーキングとして次のステップに進んでもらいます。
学位取得後に留学を希望する場合には海外留学のコースもありますし、例えば地元に戻って開業をしたいと考えている場合には、専門医資格取得後に一度大学に戻って、より専門的なことを学んで開業準備をする選択肢もあるでしょう。岐阜県に関しては、すべての領域が学べるのは岐阜大学だけですので、カンファレンスで他のチームがいまどのような治療を行っているかを学ぶことも重要な経験です。整形外科領域においては、常に自分の専門外の知識もアップデートできる環境が整っていますし、専門医資格取得後の学びとしても極めて有益だと思います。
医師の育成においてはどのような方針を持っていらっしゃいますか?
私自身、京都大学で研修を受けた後、地域医療にも携わり、一次救急から三次救急まで幅広く経験をしてきました。若手医師の頃に多くの患者さんを診て、手術も数多く経験をしました。専門医の資格を取るまでは広くいろいろな疾患を診ることや、できるだけ多くの手術に入り執刀することは大切だと思います。
もうひとつ重要なことは、疑問に感じたことをそのままにしないことです。最近はジャーナルも入手しやすくなっていますので、自分で勉強してもらいたいとは思いますが、それだけではわからないこともあります。そんなときには指導医でもいいですし、後輩でもいいので気軽に質問をしてもらいたいと思います。疑問に思ったことをその都度クリアにできる、気軽に聞ける教室の雰囲気、関係性は理想的です。
岐阜大学整形外科の医局のよいところは、みんな和気あいあいとしていて仲がよいことです。まったくギスギスしたところがないので、同年代の先生同士がお互いに相談している姿もよくみますし、若い医師も遠慮している雰囲気はありません。

今後、医局をどのように発展させていきたいとお考えでしょうか?
大学ですから、臨床と研究、教育の3つの柱を同じように発展させていくことが重要で、診療、手術と、臨床ばかりに力を入れる、あるいは研究だけ実績を残せばいいというものではありません。バランスよく進めることが大切です。
「3つの柱をバランスよく」というのは、言葉にするのは簡単でも、その実践はやさしいものではありません。しかし、医療に携わり続ける限りは、自分自身も常に学びの姿勢を持ち、知識も技術もアップデートしていく必要があります。特に大学の医局にいる医師には最新の情報に敏感に対応してほしいですし、知識、技術を磨き続けてもらうこと、それを発信していくことが大切だです。
研究においては、基礎研究だけでなく臨床研究を学会や英語論文にして積極的に発表していくことを教室員には常々話しをしています。若手医師の育成では、一般的な整形外科医療や最新の情報を伝えていくだけでなく、どうやって勉強すればよいのか、どんな学会に参加すべきかなど、具体的に学び方を含めて指導していくことでそれぞれの先生方の成長を期待し、またそれらの先生方が次の世代を育成していく継続は重要です。
最後にメッセージをお願いします
整形外科領域の運動器疾患に興味がある人であれば、ぜひ整形外科医を目指してもらいたい。もちろん整形外科領域の疾患すべてでなくても、脊椎の疾患あるいは外傷、小児や高齢者の骨格の病気など、一部でも構いません。運動器の疾患に少しでも興味があれば、整形外科に進んでもらいたいと思います。
整形外科では、手術の必要のない患者の保存的治療も整形外科医が行います。また、私たちの教室はリハビリテーション科もありますので、リハビリテーションの専門医を目指す道もあります。実際に関連病院でリハビリテーション医として活躍している医師もおり、運動器疾患に関心がある先生には、岐阜大学整形外科講座はよい学びの環境があると思います。
岐阜大学医学部附属病院 整形外科

- 卒業大学構成比
- 岐阜大学70.0%、他大学30.0%
- 男女構成比
- 男性90.0%、女性10.0%
- 活動中の主な学会
- 日本整形外科学会、日本人工関節学会、日本軟骨代謝学会、日本骨代謝学会、日本リハビリテーション医学会、日本手外科学会、日本脊椎脊髄病学会、日本リウマチ学会、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会、日本肩関節学会 他
開講60年以上の歴史を持つ岐阜大学医学部整形外科は、コンピューター支援手術や低侵襲の関節鏡、脊髄内視鏡などを使った最先端医療を提供。指定難病の新規治療法確立に向けて研究にも注力している。
研修プログラムの詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。 岐阜大学医学部附属病院 整形外科
岐阜大学医学部附属病院整形外科スタッフ紹介(2018年4月現在)
- 教授
- 秋山治彦先生
西本 裕先生
- 准教授
- 松本 和先生
- 特任准教授
- 青木隆明先生
伏見一成先生
- 講師
- 野澤 聡先生
永野昭仁先生
- 助教
- 平川明弘先生
寺林伸夫先生
岩井智守男先生
神田倫秀先生
河村真吾先生
次田雅典先生
- 特任助教
- 小川寛恭先生
田中 領先生
- 医員
- 浅野博美先生
- 大学院
- 佐竹崇志先生
竹内健太郎先生
川島健志先生
宮川貴樹先生
中村 寛先生
2018年6月掲載
研修医のための大学医局紹介一覧
大学医局でのキャリアについて、それぞれの特色を教授・医局長・先輩医師に伺いました。
-
- 岐阜大学医学部附属病院 整形外科

- 教授/秋山 治彦 先生
-
- 杏林大学医学部付属病院 整形外科
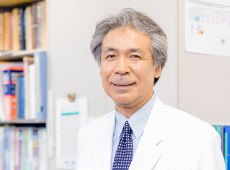
- 教授/市村 正一 先生
-
- 埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科(脳血管内治療科)
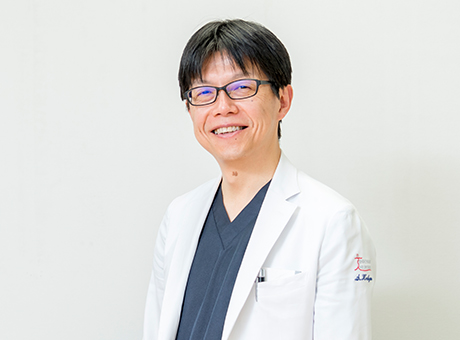
- 教授/神山 信也 先生
-
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院 乳腺科
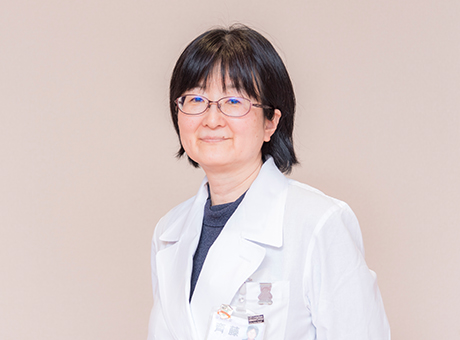
- 教授/齊藤 光江 先生
-
- 藤田保健衛生大学病院 総合消化器外科

- 教授/宇山 一朗 先生
-
- 北海道大学病院 脳神経外科

- 診療講師/医局長/長内 俊也 先生





