北海道大学病院 脳神経外科 先輩医師に聞く 医局員の日常
最短で専門医資格が取得でき大学院で基礎研究にも集中できる環境
北海道大学医学部入学の動機を「医学研究に関心があった」と語る高宮宗一朗医師。初期研修、後期研修を受けるなかで「臨床のやりがいも実感できた」と話します。専門医資格取得までの道のりと現在の活動について伺いました。
専門医資格に必要な症例を
幅広く経験できる後期研修
-
北海道大学病院
脳神経外科 医員 - 高宮 宗一朗先生
後期研修で北海道大学病院脳神経外科を選択した理由を教えてください
私はもともと研究者の道に進むため、理工学系の学部への進学を考えていました。そのなかで、医学系の研究の幅広さに関心を寄せるようになり、北海道が地元だったこともあって北海道大学医学部に進学しました。初期研修も母校で受けましたが、北海道大学病院の初期研修プログラムは、“たすきがけ協力病院”と呼ばれる協力病院と大学病院で初期救急やプライマリ・ケアなどを学ぶのが特徴です。私は最初の1年を出身地の十勝に近い帯広厚生病院で過ごし、2年目は大学で研修を受けました。
脳神経外科に関心を持ったのは、大学5年次臨床実習で全科をまわったことがきっかけでした。そのときは手先を使うのが好きだったことや神経系も奥深くて興味深いと思った程度で、膠原病内科にも関心があったので、6年次臨床実習では脳神経外科と膠原病内科を選びました。初期研修の間も脳神経外科か膠原病内科のどちらかに進むことになるだろうと考えてはいたのですが、最終的に脳神経外科に入局する決め手となったのは、脳神経外科の先生方に声をかけてもらったことや、当時教授だった宝金清博名誉教授が研修医にも気さくに接してくださるなど、医局の雰囲気のよさを感じたことでした。
後期研修の感想や印象に残っていることを教えてください
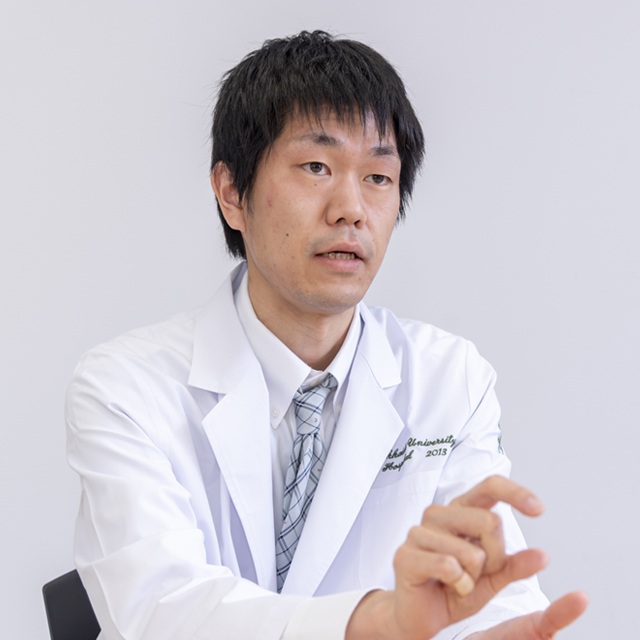
脳神経外科に入局後、大学で半年、札幌麻生脳神経外科病院で1年、大学で半年、5年目の前半に手稲渓仁会病院で研修を受けました。最後は大学に戻って病棟のサブチーフ、半年間チーフレジデントを務めました。
大学は脳腫瘍のがん化学療法や放射線治療などの専門的な治療を行うため、他医療機関から紹介患者さんが集まります。小児の患者さんの症例が経験できるのも大学ならではでしょう。逆に脳梗塞やくも膜下出血などの患者さんを大学で診ることは少なく、連携施設で脳卒中患者さんの症例を数多く経験しました。また、大学では主治医である上級医のもとで研修医が学びますが、連携施設では研修医が主治医となるケースが多く、役割が異なります。他の医療機関で後期研修を受けている研修医が専門医資格受験に必要な症例数が足りずに北海道大学病院に来ることもありますが、北海道大学病院脳神経外科で後期研修を受けていれば、専門医資格受験に必要な症例は十分に網羅できます。
脳神経外科領域は生命と直結する領域であり、脳梗塞や脳出血などで救急搬送されてきた患者さんなどの場合、確かに治療には限界もあります。しかし、たとえば超急性期の脳梗塞が完成する前に血栓回収療法を行うことで血流が再開し、麻痺で動かなかった人が動くようになるなど、目にみえて効果が実感できることもあります。自分が行った治療で患者さんの生命を救えたときの達成感は非常に大きく、脳神経外科の魅力のひとつだと思います。
臨床での研修と並行して専門医試験の準備を進めますが、教室の脳神経外科専門医の合格率100%が10年以上続いていて、「北海道大学病院で研修を受けているのだから大丈夫」という雰囲気があります。それは受験前の研修医にとって大きなプレッシャーでもありました。
しかし、受験してみて上級医が言っていた「大丈夫」の意味がわかりました。とくに筆記試験合格後の口頭試問では、毎週行われている総回診の前の症例検討の経験が活きたと思います。専門医試験の口頭試問では、施設によっては経験がないような症例が出題されることもあると聞きます。しかし、大学は豊富な症例があり、研修医は毎週の症例検討のなかで前週の手術症例と今週の手術の術前検討などを上級医にプレゼンテーションし、上級医からの質問に答えなければなりません。研修医はどんな質問が来るかを想定したうえで準備をしなければならないので大変なのですが、その日々の積み重ねで自然と多様な疾患の知識が身についていました。2018年に脳神経外科専門医の資格を取得し、続けて日本脳神経血管内治療学会専門医の資格も取ることができました。
現在はどのような活動をされていますか
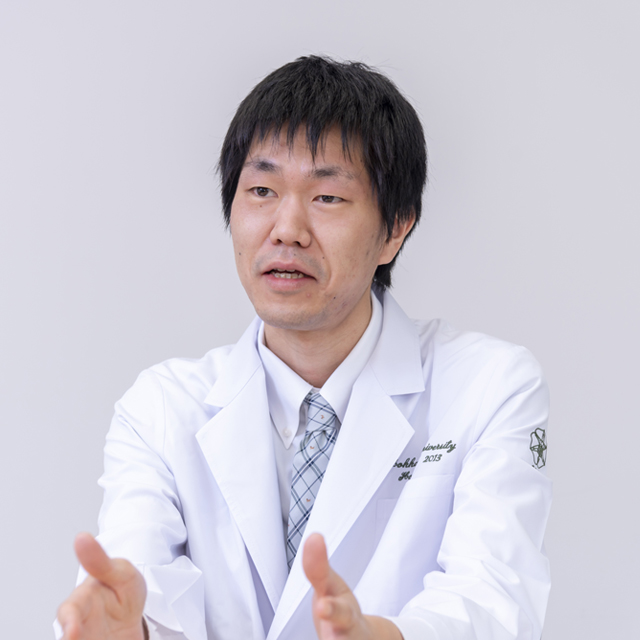
後期研修でチーフレジデントを終えた後、脊髄・機能外科班の先生たちから声をかけていただいたことがきっかけで、脊髄・機能外科班に入り、同時に大学院に入学しました。1年目は柏葉脳神経外科病院に勤務していたこともあり、基礎研究はあまり進んでいなかったのですが、先輩から「大学院での研究が軌道に乗るまでは臨床を抑えたほうがよい」とアドバイスされたこともあり、大学に戻ってからは、当直勤務以外は臨床を離れて研究中心の生活を送っています。
私自身、もともと医学研究に興味を持って医学部に進学したので、大学院に進むことは前から決めていました。現在は再生医療の研究に取り組んでいます。先生に指導を仰ぎながらも、最後は自分でやっていかなければならない大変さはありますが、結果が出ることの喜びも感じられます。
一方で臨床での経験は研究とはまた違う達成感ややりがいが感じられるものです。研究に取り組むことで臨床の奥深さを、臨床の経験を積むことで研究の楽しさがより感じられるようになりました。研究の目処が立ったら臨床の割合も徐々に増やしていきたいと考えています。
大学院修了後は脊髄領域を柱に臨床と基礎研究どちらも続けていきたいと思っています。臨床では、脊髄・機能外科班として活動するためにももっと脊髄の手術経験を積む必要があると考えていますが、今後については決まってはいません。ただ、将来的には医師としてのひとつの経験として、留学したいとは思っています。
1週間のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 研究 | 研究 | 研究 | 研究 | 研究 | 休 | 休 |
| 午後 | 研究 (夕方: 総回診出席) |
研究 (当直) |
研究 | 研究 (当直) |
研究 | 休 | 休 |
最後にメッセージをお願いします
上級医との関係も良好で、相談しやすい雰囲気があると思います。北海道大学病院は伝統的に外科手術の技術が高い医師が多く、脊髄・機能外科班からも数多くの著名な先生が出ています。後期研修の間は大変ではありますが、学年が近い先生たちと一致団結して乗り越えていくので絆も生まれますし、手術トレーニングを積むにも非常によい環境が整っているのではないでしょうか。脳神経外科医として高い志を持っている人にとっては、得られるものが非常に多い医局だと思います。
脳神経外科は多忙なイメージが強いと思いますが、どの診療科で後期研修を受けていても多忙な時期は必ずあると思います。最近は働き方改革を進めていることもあって、完全週休1日、また半年に一度は1週間の長期休暇も取得できるようになっていて、環境は改善されてきていると感じます。脳神経外科に関心がある人に入局してもらえたらと思います。
2019年6月掲載
研修医のための大学医局紹介一覧
大学医局でのキャリアについて、それぞれの特色を教授・医局長・先輩医師に伺いました。
-
- 岐阜大学医学部附属病院 整形外科

- 教授/秋山 治彦 先生
-
- 杏林大学医学部付属病院 整形外科
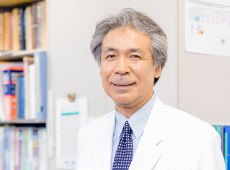
- 教授/市村 正一 先生
-
- 埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科(脳血管内治療科)
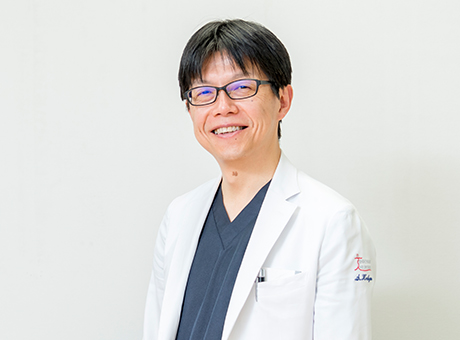
- 教授/神山 信也 先生
-
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院 乳腺科
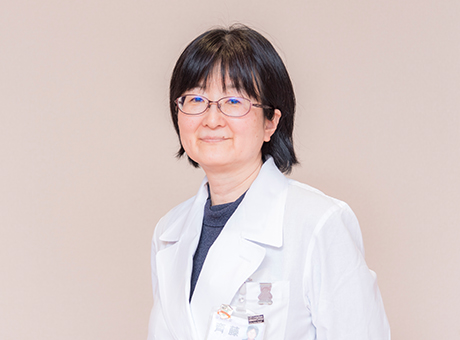
- 教授/齊藤 光江 先生
-
- 藤田保健衛生大学病院 総合消化器外科

- 教授/宇山 一朗 先生
-
- 北海道大学病院 脳神経外科

- 診療講師/医局長/長内 俊也 先生





